前略、
オーストリッチの自転車用バッグ。これを買ったのはダホン車を買う前で、以前の自転車で使おうと思っていた。バッグを買ってから自転車を買い替えたので取り付けに少しうまくいかないところがある。

ハンドルバーの後ろに付ける「F-TB フロント〜ト」。折り畳み自転車などに多いT字型のハンドル専用で取り外したときは普通のトートバッグとして使える。バッグに付いているベルクロでハンドルバー2ヶ所とハンドルポスト1ヶ所をとめて使用する。

スピードP8にはハンドルバーの高さを調整できるシステムが付いていて、その固定レバーがハンドルポストの後ろに少し突き出していて、バッグが当たってしまう。取り付けられないことはないが、スマートではない。あと現物を見ずに通販で買ったら思っていたより小さかった。これはこちらの勝手な思い込み。

サドルの下に付ける「LP-02 サドルバッグ」。これも折り畳み自転車などの小さなタイヤの自転車専用。サドルからタイヤまでの長い空間を利用した大きなサドルバッグ。サドルの下に付いている二本のやぐらそれぞれとサドルポスト2ヶ所にベルクロで固定して使用する。

これまたダホン車に買い替えたためにちょっと困ったことになった。スピードP8はサドルの固定方法が、一般的な2本のやぐらに固定する方法ではないマイナーなI-Beamシステムという方法なのだ。サドルを下から見るとTの字にプラスチックが通っていて、縦に通った長いレールにサドルポストを固定する方法だ。ダホン車の他の車種のサドルではこのレールとサドルの間が素材で完全に埋っているものもあるようだが、スピードP8では幸いT字の部分とサドルの間には空間が空いていて細いものを通せるようになっているので、本来なら2本のやぐらそれぞれに通す二本の固定ベルトを両方とも一本のレールに巻き付けてなんとか固定できた。もう2ヶ所、サドルポストに固定するので問題ないだろう。
草々
前略、

ダホン・スピードP8という自転車を最近買った。アメリカで折り畳み自転車を主に作っているDahon社(米本社サイト)の製品。
ヨーロッパ製の折り畳み自転車にもいいものがたくさんあるのだが、どれもかなり高くていいものはどれも十万円はくだらない。無理すれば買えないこともないかもしれないが、そんな高級車に乗ってしまうと落ち着いて自転車から離れていられなくなりそうな気がした。ダホン社にも十万円以上するものがたくさんあるが、この会社のいいところはバリエーションの多いところだ。ほんの数万円から切れ目なしにたくさんの車種があって自分に合ったものを選べる。
スピードP8は中級車のなかでコスト・パフォーマンスが高いといわれているようなので選んだ。最初は同じ形のフレームでひとつグレードの低いヴィテスD7あたりにしようと思っていたのだが、いろいろ見ているうちにやはりちょっといいのがほしくなり、そこそこ安い店もあったのでスピードP8にすることにした。

それまでも十年ほど折り畳み自転車を使っていたが、変速のない安物(丸石自転車のあらら)に乗っていた。折り畳み方は特に違いはないのだが、折り畳みの早さや簡便さはかなり違っていた。ダホン車の折り畳み方法は極々一般的なもので、サドルを下げ、ハンドルとフレームを二つ折りにするものだが、ハンドルとフレームを固定から開放するシステムが洗練されていて楽なのと、サドルを下げたときにサドルポストの下端がフレームから出で車体を支えるようになっているため、車体を手で持ち上げたり、支えたりするする必要がほとんどなく折り畳むことができる。そして折り畳んでくっつく前後の車軸の近くのフレームに磁石とスチール板が付けてあってくっつけてがっちりと固定ができる。
公称15秒。急がなくても30秒もあれば折り畳んだり、展開したりできるだろう。
しかし瑕瑾もある。まずハンドルポストの折り畳み部分の固定解放レバーが折り畳んだときにフレームにあたってこすってしまうこと。レバーにはビニールのカバーがついているので大丈夫だろうとほおっておいたらフレームのあたる部分がだんだん剥げてきてしまった。対策としてレバーの該当部分にさらにビニールテープを巻き、フレームの方もクッション材とテープで保護した。もちろん美しいものではない。
もうひとつはハンドルが折り畳み時にフレームの間(二つの車輪の間)に挟まるようになっていて、まず二つ折りにする前に高さを変えられるようになっているハンドルバーを伸ばさなければならず、折り畳み時にうまく車体のスタンドバーなどに干渉しない長さにするのがちょっと面倒くさい。さらにブレーキレバーの角度によっては折り畳み時にタイヤなどに接触したり押し付けたりする形になって気持ちがよくない。これを防止するためにはハンドルバーの固定レバーを緩めてバーをちょうどいい角度に回転させればよいのだが、ここまで手間をかけるとちょっと面倒になってくる。
でもまあそれでも折り畳みは簡単。アパートの上の階に住んでいて自転車はいつも部屋まで持って上がっている。前の折り畳み自転車では折り畳むのが面倒なのでそのままかついで階段を上っていたが、ダホン車にしてからは下で折り畳んでから持って上がっても全く苦ではなくなった。むしろ持ちやすく、少し軽くなったので楽になった。これからどんどん乗り回していきたい。
草々
前略、

もうひとつ気になっていたのが、同じツヴィリング社のツインSというタイプ(右)。
折り畳み方がより洗練されていて、フラットに、さらに薄くなる。こちらは3600円ほど。
こっちもほしくなったので、今度は都会にある別の小物屋に行くと、この爪切りと同時にまたしても見つけてしまった(左)。
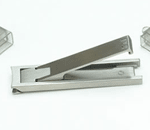
むむむっ…。前回買ったものはドイツでは一般的なデザインでいろいろな会社からほぼ同じ形の爪切りが作られているようだったのだが、これはオリジナルなものと思っていたのに。こんなにそっくりなものがあるなんて。店ではこの日本の貝印社の商品は2600円くらいで売っていた。
始めてこれを見たときは、全く同じものだと思った。日本で作ったものをドイツに供給して相手先ブランドで売る、いわゆるOEMというやつなのだと。あるいはその逆か。それだったら同じものをわざわざ高いお金を出して買うことはないと思った。
しかし、よくよく見てみるとそれぞれのブランドのロゴやマークが彫ってあること以外にもハンドルの溝やヤスリの付け方などの差異があったので、やはりこれらは違うものだろうと結論した。つまりはこの貝印はパチモンだと。
で、今回はオリジナルのツヴィリング社のものを買った。
でも現在メインで使っているのは、前回紹介した韓国製のほうである。最初の方にもかいたが、ぼくは深爪しておくタイプで爪の両端の肉との境の部分に爪切りの刃を食い込ませるので、ツインSのほうはデザイン上、刃の部分が太くて使いにくかったのだ。
コンパクトなのでかばんの中に常に入れている。
草々
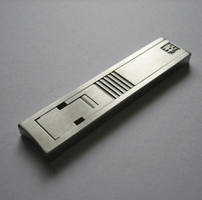
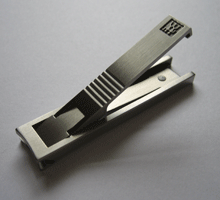

前略、

気に入ったのは、このドイツのツヴィリング社の折畳み式爪切り。三つ折り式で日本の折り畳み方とは違っていて、とても薄くなるので旅にもいいと思った。
でもさすがに爪切りに5000円以上は出せないと躊躇していたら、この形の爪切りはドイツでは一般的らしく、全く同じ形のものがドイツの他社からも出ていて安いものもあった。さらにうろうろしていたらドイツから並行輸入して安く売っているサイトがあった。送料を払ってもまだ安い。
ここで買おうかと思ったけど、その前に店でさがしてみようと出かけた。
デパートにはツヴィリング社のものがありました。正規と全く同じ値段で。さらに小物屋の爪切りコーナーに行くとありました。パチモンがっ!
韓国製とどこ製か分からないもののふたつ。どこ製か分からないものはツヴィリング社のものの全くのコピー、韓国製のものは構造は同じだが独自の作り方のもの。韓国製は1200円ちょっとで、もうひとつのものは1000円もしなかった。
さすがに1000円もしないやつはやすりのところなんかの仕上げも粗かったので、ほかも推して知るべしだろうと、韓国製のものを買った。
結構使えますよ。5000円のものは買っていないので比べられませんが。
まだつづく


前略、

日本のオーソドックスな形の爪切りで気に入ったのは、日本橋木屋の黒い爪切り(オフィシャル・ウェブ・ショップ)。
オーソドックスなものが使い慣れていて結局は使いやすいのだが、普通のものはあきちゃったので他にもいろいろさがしてみた。
つづく
前略、

年末に爪切りがこわれた。
ハサミ型のものを使っていたのだが、ハサミを開いた状態にしておくバネの針金が折れてしまった。
深爪を維持しておくタイプなので、ちょっといいものをと思って買ったのだが、これはあまりよくなかった。こわれてしまう前から支点部分の留めが甘くなり刃がうまく合わなくなって切りにくくなっていた。
ちょっといいものといっても、比較対象は100円ショップのものよりという程度で、しかも近所の店にあるもののなかで選んだので、1000円ほどのものだった。
今度はもっといいものをと思ってネットで物色を始めた。
爪切りごときでもけっこう値段も形もいろいろなものがあるのだった。
つづく
前略、
焚き火野宿大会が近づき、選択を迫られた。
一次会の焚き火焼き芋大会のみ出席して、野宿大会をパスするか、はたまた野宿もするか。
野宿するには持っている装備が貧弱すぎた。夏用の羽毛寝袋があるだけだった。マットを買えば済むような問題とも思えなかった(リッジレストを買う前の話)。なにせ夏用の寝袋なのだ。野宿初心者のぼくにはテントくらいないと到底耐えられそうになかった。
なにか安いのでいいから買おうと、最初の選択肢に浮かんできたのが、ロゴスという会社の「TDラピーダ」というテント。この製品の最大の売りは設営が簡単なこと。本体とポールが一体化していて、折り畳まれたポールも簡単に一本になるので、折畳み傘を開くようにテントが立つらしい。ナチュラムのサイトでは半額以下の7000円弱と安いし、これしかないと思ったのだが、いや待て、3.4キロは重いぞ、耐水圧も低いぞと気付いてしまった。
同じメーカーの「クイックツーリングドーム200」なら、値段もほとんど同じで3キロと軽い。でも耐水圧はやっぱり低い(耐水圧が低いと長雨だと水がしみてくるそうだ)。
さらに同じところの「ツーリングドームDX」だと、耐水圧は1500ミリだし、重さも2.5キロではないか。ちょっと高いが、もうこれだと思った。10000円弱の結構安いサイトも見つけた。が、デザインがダサいんじゃないかという印象がぬぐえなかった。
その時、コールマンの「コンパクトツーリングテントST」を見た。おお、結構かっこいいじゃないか。前室(テントの入口を出たところのタープが地面の上に張りだした部分のこと)も広そうだし。耐水圧も変わらない。あ、でも13000円弱で3.5キロもあるな。
コンパクトツーリングテントSTの「ST」とはスタンダードのことだった。ではいいのもあるということだ。そのいいやつ、「コンパクトツーリングテントDX」は何が違うのか。ポールが違うのだった。今までのものは全部ポールがグラスファイバーだったのだが、こいつのポールはアルミ合金(ジュラルミン)で軽くて、強いということだ。それで重さが2.9キロに減量している。いいテントは決まってポールがアルミ合金なのだ。安物はグラスファイバー。いいのがいいに決まってるじゃないか。でも、どこを見てもだいたい20000円前後はしていた。うーん、そこまでは出せないな。アウトドア人じゃないし、旅人だけど、旅に3キロもあるテントなんか持っていかないし。
やっぱり、ロゴスのツーリングドームDXにするかなと思ってたら、コンパクトツーリングテントDXの安いサイトが見つかった。15000円は安いぞ(ずっとあるかどうかは知りませんが)。
って訳で結局これを買いました。コールマンはロゴをみても分かる通り、もともとランプのメーカーらしく、テントは筋金入りのアウトドア人にはそんなに評判がいいわけでもないし、アメリカのコールマンのサイトにはこのテントは載っていないから、日本のコールマンの企画商品かもしれないけど(ガイジンさん向けのテントは多分ばかでかいのでしょう)、まあとりあえず判断は使ってからしてみます。
草々
前略、
来年早々に行う予定の焚き火焼き芋野宿新年会にむけて、たらたら準備中だ。焚き火コンロやバーベキューグリルを手作りしたりしている(野宿野郎ウェブログ参照)。
そろそろ自分用のマットでも買おうかと思った。マットというのは、テントや地面の上で防寒用に寝袋の下に敷くマットのことである。
いままでの野宿大会では友人のマットを借りていた。いつも借りっ放しでは悪いのでいろいろとネットなどで物色していたのだが、ただのマットでもいろいろな種類があることが分かった。旅はそこそこしているが、アウトドアのことは何も知らないぼくには驚きだった。
一番シンプルでポピュラーで安いのが、アウトドア界では「銀マット」と呼ばれている1センチくらいの厚さで片面に薄いアルミがくっついている青いポリエチレンのマット。これはさすがにぼくも知っていた。海外旅行しているときにガイジンさんがバックパックにまるめてくっつけていたのをよく見ていたからだ。1000円もしないのでアウトドア界のデファクトスタンダードとして君臨している。
一方、高級マットとして名を馳せているのが、セルフインフレータブル・マットと呼ばれている空気の入るポリウレタンフォーム製のマットで、栓を抜いて圧縮すれば空気が抜けウレタン自体も小さくなるのでコンパクトに収納でき、使用するときも栓を取ればウレタンの復元力である程度自分で膨らむ(セルフインフレート)というもの。こちらは4000円くらいからあり、高いものは15000円以上するものもある。枕で有名なテンピュールも素材は同じポリウレタンだ。
いろいろ調べてみると、セルフインフレータブル・マットは小さく収納できるのが最大のセールス・ポイントなので、地面に敷いて寝たときの暖かさはそれほどではないという意見が多かった。さらに空気式のマットなので穴が開くと当然空気がもれる。自分で膨らむのだが、膨らませた状態で栓をして使用するものなので、穴が開いて人が載るとしぼんでしまう。
あまり取り扱いに気を使う製品を高い金を出して買うのはいやなので、この手の製品はやめることにした。
結局買ったのは、この中間の価格の製品で「リッジレスト」という商品。
製品の性格は銀マットに近い。素材も同じポリエチレンだが、素材に空気がたくさん含まれているので断熱性があり暖かく柔らかい、かさの割に非常に軽い。値段は3000円ちょっとからある。
使用者の意見によると銀マットよりはもちろん、セルフインフレータブル・マットよりも暖かいというから、いいことずくめのようだが、もちろん欠点はある。大きなものがある。大きなものなのだ。
非常に軽いが、かさがばかに高い。銀マットと同じように巻いて収納するのだが、銀マットより厚いので収納サイズはより大きい。ぼくが買ったのは120センチのショートサイズだが、それでも結構な大きさだ。店に180センチのレギュラーもあったのだが、これはとても持ち歩ける代物ではないと思った。レギュラーもショートも値段はたいして違わないので、とりあえずレギュラーを買って、でかすぎれば切ればいいという意見に納得する部分もあったのだが、結局ショートにした。
さっそく家で敷き毛布とシーツの下に引いて使っている。
草々
前略、
スカイプ始めましたが、うちのコンピューター(Power Mac G4 Cube)には、音声入力端子がなかったので、そのための製品を物色しました。
考えられる選択肢は大きく分けてふたつ。
ひとつは、USB接続のマイクやヘッドセットを買う。
もうひとつは、USB接続の音声入力端子の付いたアダプターとそれにつなげるミニジャック接続のマイクやヘッドセットを買う。
ほかにもブルートゥースなどが考えられますが、5歳になろうとしているCubeには今さら多額の投資はしていられないので無視しました。
一つ目の選択肢の利点は、ブツがひとつで済むのでシンプルでいいということ。
二つ目の利点は、つないだヘッドセットなどの装置が気に入らなくても比較的安価に取り換えられるということや、アナログ音源(ラジオやレコード、カセットテープ)をデジタル録音したりなんかもできるようになることなどがあります。
なんかこういうふうに書いていたら、二つ目の選択肢のほうがいいような気がしてきましたが、結局買ったのはUSB接続の受話器型のもの(サンワサプライ USBハンドホン MM-HSUSB2)。ヘッドセットの手ぶら通話も捨てがたかったのですが、コンピューターに受話器がつながっている図がちょっと変わってていいかなと思ってこちらにしました。
買ったのはちょっと探した中では一番安かった通販サイトのケイスター。送料別でクレジットカードが使えないので振込料も必要だが、それでもまだAmazonなんかよりはだいぶ安かった(3750円+送料300円)し、即納でした。
下に今回、購入を検討した物件をあげておきます。
草々
[音声通話準備編につづく]
[初代 iPod touch でSkypeする。]
前略、

旅人としては手回し充電の商品は気になるところ。以前からこの手のラジオはあったが、でかくて高かったので旅向きではなかった。東芝のこの商品(TY-JR10)は小さいし、LEDのフラッシュライトがついていたり、軽い防水仕様になっていたりと、かなり旅に向いている。
とはいうものの、なかなか購入に踏み切れない点もある。
まずFMがモノラルというのはちょっとマイナス。5000円という値段もちょっと高い。
そしてこの商品の売りのひとつである携帯電話の充電機能というのがぼくには不要なもので、もしこれがiPodの充電にも対応してくれていたりすると、即購入となるのだが。
これだけiPod関連商品があって、乾電池式のバッテリーパックや車載ユニットや太陽電池式の充電ユニット(「Solio」)はでていても、手回し式はまだないようだ。どこか作らないかな。
草々











