前略、
サンタ・モニカからサン・ディエゴを廻り、ロサンゼルス経由で早朝にラス・ヴェガスのバス・ターミナルに到着した。1時間ほど明るくなるのを待って安宿に投宿し、夜行バスでよく眠れなかったので早速ベッドに入った。
昼過ぎに起きてまわりをぶらぶらして宿に帰って旅人たちと話をしていたら、英語の「エイ」というところを「アイ」と発音する男がいた。オージー(オーストラリア人)かと思って尋ねたら、イギリス人だという。では、ロンドンからかと聞くと、そうだと答えた。
エディというその男は25〜30歳くらいで、国では牧場で働いていて牛の乳を搾ったりしているらしい。彼と話しているうちに彼はこの後、レンタカーを借りてグランド・キャニオンに行くつもりだということが分かった。
ぼくもこの後はそこへ行くつもりだったので、彼に車代をシェアするから一緒に乗せていってくれないかと頼むと、彼はすぐにオーケーしてくれた。その後、同じ宿にいたドイツ人も行きたいというので、みんなでシェアして次の日にでも出発しようと、話はとんとん拍子に進んだ。
その夜はカジノ見物ヘ。「サーカス・サーカス」などを見物する。
次の朝、エディに起こされてグランド・キャニオン行きを1日延ばして次の日にしたいといわれる。こっちは全く急いでないので、いいと答えて、そのまま再び眠った。
昼前に起きて、昼食をエディと食べに行く。ここではコンヴィニエンス・ストアのセヴン・イレヴンにもスロットマシンがある。彼は前の晩、カジノでスタッド・ポーカーをしてかなり儲けたということだ。
ラス・ヴェガスは砂漠の真ん中にある街なので毎日晴天だった。そこは周りの全く不毛な土地に比べれば、少しは「肥沃な平原(Las Vegas=スペイン語)」だったらしい。そんな明るい太陽の下で、ぼくは日光浴、エディはやたらと電話ばかりしていた。掛ける金もない旅人は明るいうちからカジノに行く気になんかならないのである。
宿でエディと雑談をしていたら、彼の財布からイギリス・ポンドの紙幣が出てきた。彼はそれをぼくに見せ、ぼくにも日本のものを持ってたら見せてくれないかというので、荷物の底から引っ張り出して1万円札を彼に見せてやった。
その日の夕方になって、エディがモーテルに宿を移ろうと言い出した。明日はグランド・キャニオンに向けて朝早く出発したいから、そのほうが便利だというのだ。ぼくはモーテルに沿まるほどの余分な金はないからといって反対した。
彼は宿代は自分が出すからというので、そこまでいうのならと近くのモーテルに移った。
夜になると、外出していたエディが帰ってきて、面白いバーがあるから行かないかと誘ってきた。少し行ったところにトップレス・バーがあるそうだ。モーテルの時と同じ理由で断る。 すると、彼はまた金は自分で出すからといい出した。
その日、彼はやたらと気前がよかった。カジノでよほど儲けたのだろう。結局、それまで泊まっていた宿で一緒だったスウェーデン人も誘って行くことになる。
バーはフロアに三つほどの小さな円形のステージがあって、そこで女の子が順番に入れ代わりながら踊り、客は酒を飲みながらそれを見物するようになっている。バーは大しておもしろくなかった。胸ばかりやたらでかい白人娘の裸を見ても全くいやらしい感じがしないし、それに裸といっても見せるのは胸だけなのである(これはトップレス・バーなのだから当たり前)。
女の子はエディがチップをはずんだので、我々の目の前で踊ってくれたりしたが、ぼくは退屈していた、全く退屈していた、本当に退屈していた。本当だ!
やがて、やはり退屈したのかスウェーデン人が先に帰り、しばらくして我々も店を出た。エディは自分はカジノに寄って行くがといって、ぼくに先に帰るかと尋ねた。ぼくはエディがどんな風にカジノで儲けてるのか見たいと思ったので一緒に行くことにした。
エディはしばらく手を上げてタクシーを止めようとしていたが捕まらず、しばらくして金を補充するために、一旦モーテルに帰ることにした。ぼくとエディは歩いてモーテルに戻り、エディはポケットから鍵を出すと部屋のドアの鍵を開けた…
つづく
前略、
ミャンマーのシャン州、インレー湖畔の町ニャウンシュエに滞在していたときのこと。
現地の安宿に投宿するとフランス人のおじさんが泊まっていた。非常に明るくて活発な人で話しているうちに元ダンサーで今は振付けやパフォーマンスのプロデュースなどをしているひとだということが分かった。
さらに話をしているとたまには俳優もやっていて映画にも出ているという。
「ドーベルマン」に出ているというのだ。
「ドーベルマン」といえば日本でも1998年に公開されたヤン・クーネン監督のフランスのそこそこの大作映画である。
でもその映画は見ていなかったので、どうせちょい役で少し出てるくらいだろうと高をくくって、どのへんにでているのかと訊いてみると、いろんなところにでている、刑事の役だというので驚いた。
とはいうものの実は少し半信半疑だったので、帰国してから早速DVDを借りて見た。
ちゃんと出ていました。
彼の行ったとおりたくさん出ていました。
まず、オープニングのクレジットから名前が出てくるのだから主要人物といっていい。
まあ、物語に深くかかわる行動をするわけではないのだけれど、なんどもでてきて台詞ももちろんありました。
彼の名前はIvan Merat-Barboff。
[写真はミャンマーの宿「Queen Guesthouse」の人といっしょのイヴァン/「ドーベルマン」のなかでの彼]
草々
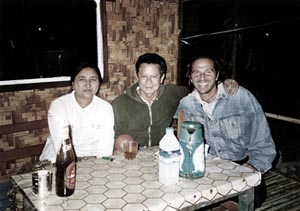

前略、
カナダで果敢にも単身でヒッチハイクをしていた女の子は、ある若い男の車に乗せてもらった。
走り出すと運転手は彼女のことをきれいだとしきりにほめ始めた。男は何度もそれを繰り返し、次に部分をほめだした。目がきれいだ、髪が…、と様々な部分をほめ続けた後、胸がきれいだなどといい始め、さらにこう切り出した。
「ちょっと、そのきれいな胸に触ってもいいか」
彼女がすぐに丁重に断ると、途中で車を下ろされてしまった。
ヨーロッパで別の女の子は、ある場所にヒッチハイクで行った帰り、再び拾った別の車が行きとは違う狭い道路に入っていき始め、そのことについて尋ねても、運転手の男たちは「大丈夫」としかいわず、頼んでも車を止めてくれなくなったので、怖くなって、車のスピードが落ちた時に飛び下りて逃げた。
ある男はアメリカでアメリカ人の旅行者と知り合い意気投合し、そのアメリカ人の車に乗せてもらい旅をしていた。
ある日、その車が故障したというので、しばらく二人でレンタカーを借りることにした。アメリカ人はクレジット・カードを持っていなかったので(アメリカではクレジット・カードがなければレンタカーを借りることはできない)、男のクレジット・カードで車を借りた。
その次の日、そのアメリカ人は男の名義で借りたレンタカーと共に消えてしまった。
警察に届けるとそのアメリカ人は国立公園を放火した前科のある連邦犯罪の前科者ということだった。
その後、レンタカー会社が車は男の名義で借りたのだから、男にすべての責任があるといって賠償を求めてきたので、彼は土地の弁護士に相談しなければならなかった。その弁護士によると男には責任はないので、早くこの州から出てしまいなさいと勧められ、そうした。
別の男はヨーロッパで大型トラックを拾った。
しばらく走っているとトラックの運ちゃんがズボンのジッパーを開けながらこういってきた。
「なめてくれないか」
男が断ると運ちゃんはあっさり引き下がったが、すぐにこう続けた。
「じゃあ、おまえのをなめさせてくれないか…」
草々
前略、
入国審査の順番が廻ってきた。いくつかの質問の後、係官が職業を尋ねてきたので、ぼくが仕事はやめたと答えると、彼は理由を尋ねてきた。
「フォー・マイ・ロング・トラベル」
英語は得意でないぼくは、自分のこの長期の旅をするためにやめたという意味でそう答えた。すると係官は自分の胸を押さえながら再び尋ねた。
「どんなトラブルだ?」
「ノー、ノー、トラヴェル!」
ぼくはあわてて下唇を噛む「V」の発音に気を付けながら訂正した。
しかし、後で考えると問題はVの発音だけではなかったようだ。
彼が「どんなトラブルだ」と尋ねた時に片手で胸を押さえていたのは、ぼくの答えの「ロング」を「ラング」(Lung=肺)と聞き取ったためだとわかった。彼はぼくの答えを「肺病のためだ」と受け取ったのである。
このことは、ぼくを少し落ち込ませたが、入国審査官に対してでたらめな受け答えをするというのは、実は悪いことではない。入国審査官が最も気を使っているのは、外国人が不法に長期滞在して働くことなので(これは当時のお話。現在はもちろんテロ関係であることはいうまでもない)、英語がうまく話せるとアメリカで働くことができる奴と見なされるのである。入国審査の時は分かっていても質問を訊きかえし、ヘたな英語で答えたほうがいいのだ。
しかし、その前にぼくは仕事をやめたと答えている。これはもちろんよくない答えである。この国で新しい仕事を探し、一発当ててやろうとしているのかもしれないと思わせるのに十分だからだ。そうはいっても、日本の会社員に長期の休暇が取れないことはかなり知れわたってしまっているので、長期旅行をする場合には答えに気をつけなくてはならない。
他には「この国に友人はいるか」という質問にも気を付けなくてはならない。友人宅に長逗留されるのを恐れているのだろう。もちろん、いないと答えたほうがよい。とにかく、自分は善意のの観光旅行者だということをよく分かってもらわなければならないのだ。
草々
前略、
世界の文字の中にはいろいろな独特の数字を表すシステムがあります。
数字を表すために独特の文字を持つところ(日本の漢数字がそうです)もあれば、既存の文字に数字を当てはめるという方法(ローマ数字がその方式のひとつです)を採るところもあります。
しかし、これらの独自方式はそれほど機能的でなかったのと「0」を表すことができなかったため、ほとんどの地域でアラビア数字が使われるようになりました(日本のように独自方式と併用しているところもあります)。
アラブ世界に行ったことのある人なら知っていると思いますが、そこで使われているアラビア数字は、我々の使用しているアラビア数字とは違うものです。現在、我々が使っているアラビア数字はアラブからヨーロッパに伝わったあとに変化したものなので、痕跡は残ってはいるもののアラブのアラビア数字とはかなり違っています。
このアラブのアラビア数字も実はアラブで作られたものではありません。アラブ人が数字交じりの文を書いているところを見てみれば、その数字のシステムがその土地で生まれたものではないことがよく分かります。
ご存じの通り、アラビア語は右から左に書きますが、数字のところに来ると彼らは少し空白をあけて数字だけを左から右へと書くのです(我々の数字と同じように一番右が一の桁)。この数字のシステムがよそから来たことは明かです。
実はアラブのアラビア数字、そしてもちろん我々の使っているアラビア数字も、発明されたのはインドなのです。アラブでは彼らのアラビア数字のことを「インドの数字」と呼んでいるそうです。
草々
追伸、
最近、旅したミャンマーでは独自のミャンマー数字が使われていました。
地元の人々は普通のアラビア数字も理解しますが、一般に使用するのは独自の数字で市バスなどにもミャンマー数字しか使われていないので覚えておかないとちょっとやっかいです。
アラビア数字との見かけの相関も若干見られるのでお隣のインドからやって来たものと思われます。
[写真はミャンマーの列車内、座席にミャンマー数字(18)が書いてある]

前略、
前回の「言葉の家族」では世界で話されている言葉のかなりの数がインド・ヨーロッパ語族というカテゴリーに入り、ひとつの祖語から分かれていったものらしいということを書きましたが、文字の世界にもたくさんの文字の共通の祖先となる文字があります。こちらは言葉とは違い遺跡として残っているので実際にどのようなものだったか、どこで使われていたかがかなりはっきりと分かっています。
紀元前1500年頃、地中海の東にフェニキアというところがありました。そこに住むフェニキア人はすぐれた航海術を持ち、商才にも長けていたので地中海沿岸の国々と取引をし、自分たちのすぐれた文化を伝えていきました。彼らの使っていた文字がフェニキア文字で、右から左へと書く22の子音を表す文字から成っていました。
この文字の源流はエジプトのヒエログリフが簡略化されてできた民衆文字(デモティック)にあるといわています。
フェニキア人が使っていた言葉はアラビア語やヘブライ語などのセム(アフロ・アジア)語族の言葉ではなかったかといわれています。これらの言語は母音が少ないので子音だけの文字でもあまり不都合がなかったということです。
紀元前9世紀頃、このフェニキア文字がギリシャに入ります。しかし、ギリシャ語はインド・ヨーロッパ語族の言葉であり、母音も多いので、そのままではギリシャ語を書き表すには不便でした。
そこでギリシャ人はこの文字にアクロバティックな独自の変更を加えます。それは文字の中でギリシャ語にはない子音の文字を母音の文字にしてしまうというものです。
この結果、A、E、O、Yが母音字となり、その後いくつかの文字を付け加え、紀元前4世紀頃、子音17と母音7の文字を持つギリシャ文字として完成します。
さらに右から左へ書いていたのも犂耕式(書く方向を一行ごとに変えていく方式)を経て、左から右へ書く方式に定着します。
これらの変更と当時のギリシャ文化の影響力から、この系統の文字は大きく広がることになります。
まず、ギリシャ文字はローマに入り(ギリシャ人とローマ人の間にエトルリア人を経由しているという説もあります)、紀元前3世紀に19文字からなるラテン語を表すラテン文字となります。
さらに紀元後5世紀頃にギリシャ文字はカスピ海と黒海の間にあるグルジアとアルメニアに入り、それぞれの言葉を書き表すグルジア文字、アルメニア文字となります。
9世紀にはギリシャ語はさらに影響力を持つ文字のお手本となります。
その頃、今のルーマニアとスロバキアの国境あたりにあった大モラヴィア公国が、今のトルコとギリシャあたりにあったビザンチン帝国にキリスト教布教のための人員派遣を要請し、皇帝はコンスタンティノスとメトディオスの兄弟を派遣しました。この時にコンスタンティノスは、当時、東ヨーロッパで話されておりまだ文字を持っていなかったと考えられているスラブ語にキリスト教の福音書を翻訳するため、グラゴール文字と呼ばれる文字を作りました。
この時彼が作った文字は独自なものだったので書くのも読むのも難しかったためか半世紀ほど後に、この文字を基にしてギリシャ文字を取り入れて作り直した文字が現れます。この文字がキリル文字と呼ばれているものです。
グラゴール文字を作ったコンスタンティノスは修道士となった後にキュリロスと名乗るようになり、これはスラブ名でキリルというのでキリル文字と呼ばれるようになりましたが、彼が作ったのはグラゴール文字で、キリル文字を作ったのは彼ではないといわれています。
ここで大きな意味を持つのが、グラゴール文字とキリル文字がキリスト教布教のために作られたということで、この文字はギリシャで信じられていたキリスト教であるギリシャ正教(東方正教)と共にスラブ語圏とその周辺地域に広まりました。そのため、現在キリル文字を使用している国は(ソ連に押しつけられた国を除いて)ほとんどが東方正教の国といってかまいません(ルーマニアは東方正教の国ですが19世紀にラテン文字に切り替えました)。
同じようにローマ・カトリックと共にラテン文字は西ヨーロッパを中心に広まりました。
話を再び紀元前に戻します。紀元前8世紀頃、アラム(現在のシリアあたり)にフェニキア文字から派生したと思われるアラム文字が現れます。
この文字は紀元前2世紀頃にヘブライ文字になり、紀元後5〜6世紀にはナバタイ文字をなかだちとしてアラビア文字になります。
ヘブライ語は紀元後2世紀のユダヤ人の離散と共に死語となり、宗教語としてのみ残っていたものを1500年以上の後にイスラエルの公用語として復活させました。その間、生きた言葉として全く使用されず変容する機会がなかったため、ヘブライ文字は22文字の子音字のみでできていて、右から左に書くなど紀元前のフェニキア、アラム文字の特徴をそのまま持っています。
草々
前略、
18世紀の末に勘の鋭いイギリス人のインド学者、W・ジョーンズがインドのサンスクリット語(仏教がかかれた言葉。般若心経の最後に出てくる「ギャーテーギャーテーハラギャーテー」はサンスクリット語が中国を通って訛りに訛ったもの)を読んでいてふと気がつきました。この言葉はギリシャ語やラテン語、さらには他のヨーロッパ語となんか似てるじゃないかと。
これまでの人は誰もヨーロッパ人が話す言葉とインド亜大陸で仏陀の時代に話され、すでに滅びた言葉に関連性があるなどということは考えもしませんでした。しかし、研究が進むうちに古い古いサンスクリット語だけではなく現在、ヨーロッパからインド亜大陸にかけて話されているほとんどの言葉にも強い相関関連があり、同じ一つの言葉の祖先を持つ家族であろうということが分かってきたのででした。つまり、これらの言葉は書き表す文字は全く違っていても類似した文法と共通した語彙を持つ仲間だということなのです。
これらの言葉はインド・ヨーロッパ語族と呼ばれ、フィンランド、エストニア、ハンガリーを除くすべてのヨーロッパ語(一部の少数民族[バスク語など]の言葉は除く)とイランからアフガニスタン、パキスタン、中央アジアの旧ソ連の一部の国とインドで話されるほとんどの言葉が含まれます。
新大陸では今や英語とスペイン語、ポルトガル語の天下で、広大なロシアではロシア語の天下、アフリカでも植民者のヨーロッパ語が幅をきかせているので、話者の数や面積でいうとインド・ヨーロッパ語は世界のほとんどを占めていて、その言葉を話さない場所をあげる方が早いくらいです。すなわち、東及び東南アジアと南インド、中東と一部のアフリカです。
これだけの大家族になると血はつながっていてもあまり似てないものとそっくりなものの違いがはっきり出てくるので、それぞれの似た小さな家族ごとに語派という形で分かれています。
英語はドイツ語や北欧の言葉などとまとまってゲルマン語派と呼ばれています。フランス、イタリア、スペイン、ポルトガルのいわゆるラテンの国の言葉はルーマニアなども加えてロマンス語派といい、ロシアと東欧、バルカン半島の言葉はスラブ語派というグループに入ります。
これらのインド・ヨーロッパ語族の中にはぽつんと孤立する例外があります。それがさきほどもあげたフィンランド、エストニア、ハンガリーで、これらの国の言葉はインド・ヨーロッパ語とは関連がないアジアから伝わってきた言葉で、アジアの騎馬民族がやってきたときに残していったものだといわれています。また、スペインの少数民族の言葉バスク語は旧石器時代にまでさかのぼる言葉ではないかともいわれています。
これらの中には別々の名前が付いていても言葉自体はほとんど同じというものもあります。例えばスウェーデン語とノルウェイ語はそれぞれの国の名前が付いていますが実際には方言以上のへだたりはないらしく、インドのヒンドゥ語とパキスタンのウルドゥ語も国と宗教、文字はが違うけれども基本的には同じ言葉だそうです。
では日本語はどのグループにはいるのか。これは昔から議論されてきた問題です。
日本語と朝鮮語は文法が非常に似通っている言葉であることは知られています。これらの言葉は膠着語と呼ばれ単語に助詞(てにをは)や助動詞などがくっついて(膠着して)文章を作ることからきています。
インド・ヨーロッパ語族の言葉は屈折語と呼ばれ、単語が変化(屈折)することによって文意を表します。英語はかなり簡略化されて屈折する部分が少なくなっていますが、他の言語では名詞の語形変化で格(主格、所有格など)を表したり、複雑な語形変化をして学習者を悩ませます。
世界の中ではアルタイ語族であるトルコ語やモンゴル語などが膠着語の仲間で一時は日本語や朝鮮語もこれらの語族とされていた時期もあったようですが、現在はここからは離れ、また似た文法を持ち文化的にも距離的にも近い日本語と朝鮮語も文法以外の単語間の相関関係が非常に低いということが同じ語族とするのをためらわせています。
では日本語はどこからきたのか。当然、どこからでもなくその場所から発生したオリジナルであるという考え方もあるのですが、どこからか来たとすると、北の中国語とは文法的に全く違う(中国語は語形変化もなければ助詞などが膠着することもなく単語の順番だけで意味を表すので孤立語と呼ばれています)ので、考えられるのは南(太平洋の島など)と西で、最近、有名なのはインドのタミル語語源説です。
タミルは南インドにあり、インドの中では数少ないインド・ヨーロッパ語族でない言葉で、映画「ムトゥ 踊るマハラジャ」や「ボンベイ」の作られたところとしても知られています。この説を発表した大野晋教授によるとタミル語と日本語の間には文法や単語の相関関係だけでなく言葉が渡ってきた場合に当然考えられる文化的な関係(カレーを米で食べる以外にも)も強く認められるとのことです。
草々
前略、
日本国内で日本人の両親から生まれて日本語でこれを読んでいるほとんどの人は当然のように日本国籍(だけ)を持っています。しかし、国籍というのは実際にはどのようにして決定されるのでしょうか。
まずは生まれてきた赤ちゃんの国籍の決め方です。
これには大きく分けて「生地主義」と「血統主義」の二つの考え方があります。
「生地主義」はその国で産まれた赤ちゃんにはその国の国籍を与えるという考え方で、イギリス連邦や南北アメリカ大陸の国々がこれを採用しています。
対する「血統主義」は赤ちゃんが父親、または両親の国籍を受け継ぐという考え方で、両親の国籍を受け継ぐ方式が多数です(日本はこれを採用しています)が、イスラム系の国などがまだ父親のみの国籍を受け継ぐという方式を採っています(といっても日本もついこの間まではこの方式だったのですが)。
国籍の与えられ方に大きく分けてこの二つの方式があるということは、両親の国籍と生まれた国によっては赤ちゃんの国籍が複数になったり、全くなくなったりする可能性があるということを意味しています。
血統主義の国の国籍を持つ両親が生地主義の国で赤ちゃんを産むと両親の国と生まれた国の二重国籍を持つし、血統主義の国の国籍を持つ国際結婚の両親から産まれた赤ちゃんも父親と母親の国の二重国籍になります。
反対に、生地主義の国の国籍を持つ両親が血統主義の国で赤ちゃんを産むと無国籍になる可能性もあるということです(たいがいの文明国ならそのあたりのことには例外規定があると思いますが)。
これだけでなく、血統主義の国の国籍を持つ国際結婚の両親が生地主義の国で子供を産むと三重国籍を持つ赤ちゃんができあがります。
ただし、すべての多重国籍者がいつまでもその国籍を保持し続けられるというわけではなく、国によってはそれを認めないところもあり、日本はそれに当てはまります。
日本の法律では、日本国籍を含む多重国籍者は22才まではそれらの国籍を保持でき、それまでにどれか一つの国籍を選択することになっています。20才以降に多重国籍になった者はそれ以後の2年以内に選択します。
20才以降に多重国籍になる場合というのはどんな場合かというと、だいたいの場合、国際結婚か帰化ということになります。
国際結婚の場合、相手国の法律によってはもれなく自動的に無理矢理にでも国籍が付いてくるという場合もあり、帰化の場合には元の国籍を離脱しなければ多重国籍になりますし、これまた法律によってもとの国籍から離脱できないという場合もあります。
日本では結婚すると親の戸籍から出て自分たち夫婦の新しい戸籍が作られるわけですが、日本国籍を持つ人の国際結婚の場合には全く同じようにはことは運びません。
国際結婚すると結婚した日本国籍者のための新しい戸籍が作られるのは変わりませんが、日本の戸籍には日本国籍をもつものしかは入れないので、ここに外国籍の配偶者は日本に帰化しない限りはいることができません。その戸籍の配偶者の欄は空で別の場所に外国籍の者と結婚した旨が記されているだけということです。
そして、特に届けることがなければ姓も変わることはありません。配偶者の姓を(日本で法的に)名乗りたい場合は結婚してから六ヶ月以内に申請すれば配偶者の姓に変更できます。配偶者が中国か韓国籍の場合は同じ漢字の姓(但し、日本の漢字と違う場合は日本の漢字に改める)に、それ以外の場合はカタカナの姓になります。
この時点ではスミスさんと結婚してこの姓を名乗ると届けた人がパスポートを取ると、その中の名前のローマ字表記は本名であるカタカナのスミスをそのまま直した「SUMISU」になってしまいます。これを「SMITH」と表記するためにはさらに届けが必要です。
その後に赤ちゃんが産まれたとします。国籍についてはこれまでに書いたとおりですが、赤ちゃんの姓についてはまた別のお話となります。
配偶者が帰化している場合は法的には日本人同士ですから我々と変わることはありません。届けを出して夫婦同姓になっている家族の場合は当然、赤ちゃんもその姓で日本国籍者の戸籍に子供として入ります。夫婦別姓の場合はなにもしなければ日本国籍者の姓で同じ戸籍に入り、届けを出せば外国籍の配偶者の姓を付けられますが、戸籍は日本国籍者の親とは姓が違うということでその子供だけのものが新たに作られます。
但し、これらの話は日本の法律に置いてということであり、多重国籍を保持している限りは他の国の法律に基づいた姓名が別にあるということになります。
帰化については、日本国籍者の配偶者であるとか、日本で生まれたとか、日本にかなり長期間住んでるとか、日系人だとか、相撲の親方になるとか、オリンピックやワールドカップで活躍しそう(しかも、本国のほうはレベルが高いので補欠)だとかの正当な、あるいは怪しい理由がなければ非常に難しいということです。
赤ちゃんが二十二才になるときがやってくると、国籍選択をしなければなりません。
日本の国籍なんかいらないという場合には話は簡単です。国籍の選択をしなかったり、国籍離脱届けを出したり、他の多重国籍を認めない国の国籍を先に選択し(その国がその旨日本政府に伝えてき)た場合には日本国籍はなくなります。
また、他の国の国籍なんかいらないという場合も簡単です。日本の国籍を選択し、他の国のは離脱すればいいのです。
この他にもまだ第三の選択の方法があるようです。
とりあえず、日本の国籍を選択します。すると、日本政府はその「元」多重国籍者が日本国籍を選択したことを他の国籍の国に伝えます。その相手国が多重国籍を認めない法律を持っている場合、その国籍は自動的に剥奪される可能性があります(日本の場合はそうらしい)が、相手国が多重国籍を認めているまともな国の場合は、自国民である本人からの届けもないのに他の国の政府のお知らせだけで国籍を剥奪するようなことはしないのです。
つまり、とりあえず、日本政府には日本国籍を選択するといって押さえておけば、(その国の法律にもよるが)他の国の国籍はほっておけば、事実上、多重国籍のままでいられる可能性があるということです。
オリンピックに出るために外国籍の日系人が日本に帰化したなんていうことがありましたが、その人たちは明らかにもとの国籍を保持していて二重国籍になっているはずです。
外国に行くときに複数のパスポートの中から一番有利なものを選んで使うなんてスパイか暗殺者みたいで怪しくてかっこいいじゃないですか。
資格、免許マニアという使いもしないのにたくさんの資格、免許をもつ人たちがいるのですから、広い世の中にはたくさんの国籍を持つ国籍マニアがいるかもしれませんね(世界最多国籍のひとは誰でいくつの国籍なのでしょう。ギネスに載ってるのかな)。
草々
前略、
ルーマニアを旅していたときの話である。
闇両替がまだ行われていたこの国では、観光客の多い大きな街にはたくさんの闇両替屋が通りに立って外国人に声を掛けていた。
両替所の前には特に多く、だます奴も多いというので、相手にしていなかったのだが、両替所を探していたときに、数人で立っていた若者のグループにレートを訊いてみた。
「650」
これはほとんど公定レートと変わらないので相手にせず、立ち去ろうとすると、いきなり800レイに上がった。これは非常にいいレートである。そこでものは試しに、そこで街頭での闇両替に挑戦してみることにした。20ドル両替するというと、彼らは不平を言った。
「もっとたくさん。50か100ドルだ」
それならもういいと、再び立ち去ろうとすると、彼らは簡単に折れた。
「オーケー、ノー・プロブレム」
彼らは20ドル分の16000レイを先にぼくに渡して確認させた。確かにあることを確認して20ドル札を渡す。
「ちょっと、待った」
隣にいた仲間の男がそういって、その札を取り上げた。
「それをよく見せてくれ。この札はちょっと変だ」
そう言いながら、男は紙幣を手の上で折りたたみ始めた。
「こら、こら、やめろ。折り畳むのをやめろ!」
その仕草は何かで読んだことがあったのだ。ぼくは16000レイをもう一人の男に突き返すと、男の手を取ってたたんだ札をしっかりと握ったその掌を無理矢理に開かせて、20ドル札をもぎ取った。
彼らはぼくがレイを返していたのにもかからず、もぎ取った札を取り返そうとしたので、彼から取り返してくしゃくしゃになった札を見てみると、そこには2枚の紙幣があった。ぼくの渡した20ドル札と、どこからか不思議な力によって彼の掌に湧き出てきた魔法の1ドル札だった。
ぼくはその1ドル札を握りつぶして通りに捨てると、そこを立ち去った。彼らはそれをあわてて拾うと、ぼくに悪態をついた。
彼らの手口は渡した現地通貨を相手に確認させて安心させて、取り引き成立と見せかけておきながら、相手の札も自分たちが確認するという名目で折りたたみ、この札は偽札かもしれないから両替はできないといって、札を突き返して現地通貨を取り戻すのである。返された札を後でよくみると、それは折り畳んだ時にすり替えられた1ドル札になっていて、その頃には連中は消えているという寸法である。
この方法はどの札も似たような色とデザインのアメリカ・ドルの場合のみ有効である。
その昔は現地通貨のほうに細工する手口が多かったようだ。単純に少ない金額を渡したり、すでに廃止された紙幣を混ぜたり、インフレが進んで価値はないが単位は大きい外国の紙幣を混ぜたりしたらしいが、いまでは旅人は用心深くなり、もらった紙幣を確認するようになったので、これらの手口は廃れてあまり行われなくなり、より手の込んだ方法が考案されたのである。
ある黒海沿岸の観光地でも、たくさんの闇両替屋たちが外国人旅行者たちに声を掛けていた。
通りの闇両替屋に声を掛ける気はもうなかったので、すべて無視して歩いていたのだが、そのうちの一人がやたらとしつこく後ろを付いてきて両替を勧めてきた。断っていると10ドルでも5ドルでもいいといい出した。そんなことを自分からいいだすやつは珍しなと思いながらも断っていたが、それでもまだ付いてくる。あまりしつこいので、そいつを巻くために大通りから折れて細い小道に入っていった。
しかし、それは失敗だった。そいつはあきらめずについてくると、ポケットからルーマニアの札束を出してみせて金は持ってるからというのだった。すると、突然、後ろから黒いサングラスを掛けた男が駆け寄ってきて叫んだ。
「ポリース!」
その男はポケットからIDを見せると、闇両替屋が持っていた札束を没収するとポケットに入れ、ぼくの腕を凄い力でわしづかみにした。
サングラスの男は再び、叫んだ。
「パシャポルト!」
どうやらぼくに旅券の提示を求めているようである。闇両替屋もおとなしく出したほうがいいというようなことをいっているようだ。しかし、ぼくは逮捕されるようなことは何もしていないのである。
「なぜぼくが旅券を見せなければならないのか。あんたは本当に警察か」
ぼくが彼にそう尋ねると、彼は再びIDを出すと、素早くその一部分を指差してみせた。その部分には確かに警察という意味らしき「…politie…」というようなルーマニア語が見えたが、彼はすぐにそれをボケットにしまってしまった。その間も彼はぼくの腕をしっかりとつかんで放さない。
「もっとちゃんとそのIDを見せてくれ。中も見せろ」
そういったが、彼はその中身をほんの一瞬、開いて見せただけで、すぐに閉じてしまった。
そのあまりに不自然な態度で、ぼくは彼が警察でないことが確信できた。
「ふざけるな。失せろ!」
そいつの腕を振り払って悪態を付くと、警察官と闇両替屋は「二人なかよく」雑談しなが残念そうに並んで去っていった。
彼らの手口は両替自体でだますのではなく、闇両替屋がカモにまともに闇両替をさせておいて、そこを警察役の奴が踏み込んで、違法行為であると両者の金を没収、あるいは逮捕すると脅して罰金を取り、後で分けるというようなもののようだ。そのため、5ドルでも10ドルでもいいといったのである。
これは当時のガイドブックにも載っていない新しい手口だった。
彼らはぼくが1ドルも両替をしなかったのにも拘らず、せっかくのカモであるし、ひょっとしたらうまくいくかもしれないと幕を上げたようだ。
警察役の男が見せたIDには楕円の中に「RO」の文宇が入ったマークが付いていた。これは車がどこの国の登録かを表すために車体につけるマークだから、あのIDは(「警察署」発行の)運転免許証だったと思われる。
気を取り直し、再び街を歩き出して30分後のこと。
「セニョール、チェンジ・マネー? セニョリータ?」
なぜかイタリア語を混ぜながら話しかけてくる別の闇両替屋が付いてきた。
適当にあしらっていると別の男が走ってきて叫んだ。
「ポリース!」
「………」
そこには詐欺師の親睦会かギルドか何かがあって、月に1回ほど集まって研究発表会を行なっているに違いない。同じ手口はトルコでも聞いたというから年に1回はジュネーブのホテルで国際詐欺師学会が開かれて意見の交換をしているのだろう。インターネットにフォーラムがあるのかもしれない。
草々
前略、
ぼくは移動手段に選択の幅がある場合、タクシーよりバス、バスより列車、列車より船というように、より車体、船体の大きい、自由に動ける範囲の広いもの(しかも安ければいうことない)が好みで、飛行機は大きな海を越えるとき以外なるべく使わないようにしている。
飛行機は嫌いなのだ。
しかし、怖いからとか落ちるからとかが理由ではなく、乗ること以外の部分に嫌いになる理由が多い。
飛行機に乗るには事前に予約をしなければならず、同じ路線でも時期や航空会社、代理店によって値段がかなり違うのが面倒で、まず気に入らない。
そして空港はどこの国でも町から離れたところにある(でも成田より遠い空港ってあるの?)。
空港へも出発の1時間も2時間も前から空港に行かなければならないし、空港内は食べ物などが高いのが気に入らない(マクドナルドの安売りキャンペーンもだいたい空港ではやっていない)。
そしてこれはなぜかは分からないし、ぼくだけかもしれないのだが、空港にいる搭乗客がみんなバカみたいに見えるのだ。バス・ターミナルや駅ではそんなことは感じないのにどうしてだろう。へんにうれしそうではしゃいでいるからだろうか。
搭乗手続きでは大きな荷物は託送荷物として預けなければならない。自分の大事な荷物を手放して他人に預けるのが気に入らないし、荷物の中身が一部なくなったり、壊れたり、違う飛行機に積まれて何千キロも離れた知らない場所へ運ばれていってしまうことがあるのも気に入らない。
出国審査を済ませると、機内持ち込みの荷物の検査がある。ガスやオイルなどの可燃物、火薬、刃物、銃器などが持ち込めないのは当たり前だが、カメラの電池が持ち込めなかったこともあり気に入らない。ちなみに、水銀式の体温計なども本来持ち込み禁止である(なんで?)。
それらを済ませ、なんとか搭乗口までたどりつく。座って待っていると、ここでいつも必ずぼくの理解できない不思議なことが起こる。まだ開いてもいない搭乗口の前で、並んで待つ人が現れるのだ。それもかなりの数の人が何分も何十分も前からぞろぞろと並び始める。すでに搭乗手続きを済ませて、搭乗券を受け取り、座席の指定も受けているのに、搭乗口の前でぼけーっと立って待つことに何か意味があるのだろうか。
搭乗手続きのために早く来て並ぷのなら分かる。窓際に座りたいとか、通路側がいいとかの希望がある場合以外にも、航空会社はいつもキャンセルを見込んで予約を実際の席の数よりたくさん受けている(オーバー・ブッキング)ので、予約していても早く搭乗手続きしないと乗れないこともあるという(全く気に入らない)。その場合でも運がよければ、ビジネス・クラス、あるいは、ファースト・クラスに追加料金なしで乗せてもらえる場合もあるそうだ(それなら許そう)。
しかし、搭乗手続きをしてしまえばそういうことはない「はず」である。最近は爆弾テロなどを防ぐなど理由で、託送荷物を預けた客が全員搭乗したことを確認するまで出発しないことになっているほどなのである(どうしても客が現れなければ、その客の託送荷物を下ろして飛ぶ)。
いい加滅な三流の航空会社になると、搭乗手続きの際には席を指定しておきながら中は自由席ということもあるから、その場合は、まあ一応、並んで先に機内に入り込むことに利点がないことはないのだが、その他に利点があるとすれば、機内の新聞や雑誌を先に読めるというぐらいしかぼくには思い付かない(日本の新聞や雑誌をおいている航空会社には滅多に乗らないぼくにはこれもほとんど関係がない)。
いつも一番最後に乗り込むぼくが知らないだけで、なにか素晴らしい利点があるのであれば是非、教えてほしい。
機内に乗り込んでも、エコノミー・クラスの席はグレイハウンド・バス並みに窮屈で、出入りがしずらいのが気に入らないし、飛行機は始終出発が遅れ、よく欠航し、時々ひどく揺れ、たまに墜落し、まれに撃墜され、宇宙人に拉致されたりするのが気に入らない。
でも、本当をいうとぼくはまだ飛行機でトラブルらしいトラブルにはあったことはないのですが。
草々
前略、
日本に住んでいて欧米の文化にばかりさらされていると、人の名前というのは順番の後先はあるにしても、個人の名と家族(一族)の名で構成されているのが当たり前だと考えがちです。しかし、他の国々を見てみるとそれが必ずしも当たり前というわけではないということがわかってきます。
世界の人名の付け方は大きく三つに分けられます。
(1)個人の名と家族(一族)の姓によって構成されるもの。
(2)個人の名と父親などの個人の名で構成されるもの。
(3)個人の名のみで構成されるもの。
(1)は説明するまでもなく、日本やその他の多くの国が採用しているシステムで、詳しくは後ほど説明します。
(2)は家族や一族で共通する姓というものはなく、個人の名と父親やそのまた父親などの名とで名前を構成するシステムです。
このシステムを採る最も典型的なところはアラブの国々です。サウジアラビアの王様の名前を例にして説明します。
例/ファイサル・(イブン)・アブドル・アジズ・(アル)・サウド
彼の場合、個人の名は最初のファイサルのみです。次にくるイブンは「〜の息子」という意味で略されることが多く、続いて彼の父親の個人の名のアブドル・アジズがきます。この後にさらにイブンと続き、祖父の名やさらに祖先の名が入ることもあります。そして、アラビア語の定冠詞のアルに続いて王族名のサウドがきています。ここには出身地名、種族名などの我々のいう家族の姓とは違うかなり大きな範囲をくくる家姓(ニスバ、家系の名ともいう)が入ります。これにより父系の祖先の出身や由緒がわかるということです。
つまり、彼の名前は「サウド家のアブドル・アジズの息子のファイサル」ということを意味しているわけです。
ちなみに彼の父の名のアブドル・アジズは二語で一つの名前を作ります。なぜならアブドルのうちのABDが「しもべ」、ULが「〜の」という意味を表すので、その後には必ず何かが入ります。彼の父の場合は「アジズ(慈悲深き者=アラー)のしもべ」という意味で、アブドラー・ザ・ブッチャー(プロレスラー)のアブドラーは「神(アラー)のしもべ」という意味です。
例/ムハンマド・ホスニ・サイド・ムバラク
ムハンマド・アンワル・(アル)・サダト
現と前のエジプト大統領です。彼らの場合二人とも最初の語がムハンマドになっていますが、彼らの個人の名前はこれだけではありません。ムハンマドはあまりにもありふれた名のため、この名前の場合は後に続く名前と二語で個人の名を構成します。(サダトは父の名の部分を省略しています)
このようにアラブの国の人たちには我々のいう家族の姓というものが(サウド家などという非常に大きなもの以外)ないので、ただ一語だけで個人を呼ぶ場合、例えば、イラクのサダム・フセイン大統領をただ、フセインと呼ぶのでは彼の父親の名を呼んでいることになります。ちなみにヨルダンのフセイン国王のフセインは彼の個人の名です。
この他、アラブ以外のイスラム系の国の一部(パキスタン、マレーシアなど)もこの名前のシステムを持っていますが、トルコやイランでは個人名と家族の姓というシステムになっています。
これらのイスラムの国の名前の理解を難しくしているものに称号というものがあります。偉い人や偉く見せたい人が、場合によっては複数の称号をつけ、ややこしくしています。日本の下司なおやじが名刺に肩書きをたくさん並べているのを連想してしまいます。
以下は典型的な称号の例です。
アミール 君主・高官
アクバル 偉大な
ハフィズ コーランを暗誦できる
ハキム 学者
マリク 国王
シェイク 族長
シャー ペルシャ国王(ちなみにこれはチェスの語源)
イスラム系以外ではモンゴルが父親の名+個人の名というシステムを持っています。
(3)は姓というものが全くなく、個人の名のみというシステムです。
インドネシアは多民族国家なのですべてがそうであるというわけではありませんが、基本的には1〜3語の個人の名のみを持っています。
一般に男性には語尾に「o」の発音が、女性には「i」の発音がつきます。さらに男性の場合は語頭に「豊かな、良い」という意味の接頭語「ス」がつく人が多いとのことです。
例/スカルノ(前大統領)
スハルト(現大統領)
デビ夫人(前大統領の何番目かのかみさん)
ビルマ(ミャンマー)も姓がなく、1〜4語の個人名を持ちます。
おもしろいことに生まれた日の曜日によって名前の最初の発音がいくつかに限定されるといった特徴があります。例えば、アウン・サン・スー・チー女史の最初の「a」の発音は日曜日生まれを示しているそうです。
元の首相にウー・ヌという人がいたそうですが、この中の「ウー」は名前ではなく目上の者に対するごく普通のの敬称だそうです。つまり、知らないうちに「ヌ様」と呼ばせてた/呼んでたということのようです。
そして、(1)に戻ると、我々に一番理解しやすい家族の姓+個人の名というシステムですが、これも日本などの中国文化圏のような姓と名がそれぞれひとつだけというところは少なく、母親や自らの旧姓やら(2)の父親の個人名などが加わってきたりで一筋縄ではいきません。
例えば、スペインは個人名+父の姓+母の姓で、ポルトガルは個人名+母の姓+父の姓になり、ギリシャ、ブルガリア、ロシアになると個人名+父親の個人名+姓のパターンになります。
例・ミハイル・セルゲイヴィッチ・ゴルバチョフ
この最初で最後のソビエト連邦大統領の個人名はミハイルで、父親の個人名がセルゲイ、語尾の「ヴィッチ」(または「イッチ」)は「〜の息子」という意味で、女性の場合は「〜の娘」という意味の「ナ」「ア」「ヤ」が語尾につきます。ちなみに「サナバビッチ(son of a bitch)」は全く関係ないことを付け加えさせておきます。
アラブの項でも出てきた「〜の息子」という意味の言葉は世界中の姓名の中に入り込んでいて、アラブやロシアのように「実際の父親の名前」+「〜の息子」というパターン以外にすでに家族の姓に転換して残っているものも多くあります。
例えば、
・ベン〜 (Ben〜) ユダヤ系
例/ダヴィド・ベングリオン(イスラエル初代首相)
・〜オウル (〜oglu) トルコ
・〜オスフィ (〜osfi) ハンガリー
・〜エスク (〜escu) ルーマニア
例/ニコラエ・チャウシェスク(ルーマニア元大統領)
・〜ウィッツ (〜wicz) ポーランド
・〜ス、〜ソン、〜セン (〜s,〜son,〜sen) スカンジナビア系
例/トーレ・ヨハンソン(音楽家)
例/ハンス・クリスチャン・アンデルセン(作家)
・フィッツ〜 (Fitz〜) イングランド
例/スコット・フィッツジェラルド(作家)
・オ〜 (O’〜) アイルランド
例/ライアン・オニール(俳優)
・マック〜 (Mac〜,Mc〜,M’〜) スコットランド/アイルランド
例/ドナルド・マクドナルド(ハンバーガー屋)
ポール・マッカートニー(音楽家)
以上はすべてそれぞれの国で「〜の息子」という意味をもつ語です。姓が下々の者までに導入される前にアラブの国のように「〜の息子」と呼ばれていたものがそのまま姓に転換していったということなのでしょうか。
また、これらの姓からは少なくとも先祖の誰か一人はその姓を持つ国からきたということが我々にもわかります。
他には、
・姓に「van 〜」がつけばオランダ系だとか、
例/ヴィンセント・ヴァン・ゴッホ(売れなかった画家)
蛇足、彼の名前はフィンセント・ファン・ホッホのほうが実際発音に近いそうです。
・ドイツの「von 〜」やフランスの「de 〜」は(元)貴族を表すとか、
例/ウェルナー・フォン・ブラウン(ロケット科学者)
エーリッヒ・フォン・シュトロハイム(監督・俳優)
シャルル・ドゥ・ゴール(ジャッカルに狙われた元フランス大統領)
クラリス・ドゥ・カリオストロ(カリオストロ公国大公息女)
そのようなこと(あるいはそう思わせたいということ)がわかります。
草々


