前略、
ブダペストではプライヴェイト・ルームに泊まった。プライヴェイト・ルームは一般の家庭が空いた部屋をホテル替わりに貸すというもので、東欧の中でもハンガリーは特にこのタイプの宿が多い。この町にもユース・ホステルもあるが、街の中心からは少しあるので不便なのだ。
ぼくの泊まったプライヴェイト・ルームにはこの頃、旅の途中の日本人が住み込んでいて、ベッドと食事だけもらって無給で客引きなどの「番頭」業務をしていた。
そこには他にも面白い日本人の旅人がいて、我々から「ホームレス山田」と名付けられたその男は、ぼくがブダペストに着いた時に、ホームにぽつんと立っているのを見かけていた。しかし、その時は声を掛けるわけでもなく通り過ぎた。
その日、そのプライヴェイト・ルームに投宿した後、この宿の番頭さんも客引きの際に駅で彼に会い、彼は我々の宿にやってきた。そして彼は驚異の超異次元体験を我々に聞かせてくれた。
ホームレス山田は、その前日にブダペスト東駅に着いた。ブダペストにはプライヴェイト・ルームの数が多いので過当競争になり、この宿の番頭さんがしているように駅での客引きが当たり前になっている。彼は客引きと交渉して、あるプライヴェイト・ルームに泊まることにした。そこで数日分の宿代を払い、彼はさっそく町へ観光に出た。
夕方、彼はその日の観光を終え、自分の宿に帰ることにした。しかし、彼はこの時すでに知らぬ間に恐怖の超異次元空間にはまり込んでしまっていたのだった。
彼はいくら歩いても自分の宿に帰りつけなかった。いくらさがしても歩き回っても自分の宿を見つけることはできなかった。彼のまわりの空間がねじれてしまったのか、知らぬ間にパラレルワールドにワープしてしまったのか、宇宙人が彼を拉致し記憶を消してしまったのか、あるいは彼の宿を消滅させたのか…。
いや、彼は迷子になってしまったのだった。
彼は自分の泊まっているプライヴェイト・ルームの場所が分からなくなってしまったのだ。彼はこの異国のまちで迷子になり、完全にパニックにおちいり、狂ったように街を歩きまわったが、自分の泊まっている場所、そして自分のすべての荷物が置いてある場所は見つけられなかった。
彼がこの日、自分の宿を見つけることを断念した時には、夜もとっぷりと暮れていたため、彼は小さなデイ・パックを持っただけで、100ドル以上する高級ホテルに泊まったそうだ。
その次の日、つまり、ぼくがこの町に着いた日、東駅でぼーっと立っている彼をぼくが見掛け、その後、番頭さんが声を掛けた。
彼がそこにいたのは、東駅で待っていたら前日、客引きをしていた男がまた客引きにそこへ来て、彼に会えるかもしれないと思ったからだそうだ。
彼はこの日も宿を見つけられずに我々のプライヴェイト・ルームに泊まり、次の日ついに、ついに自分の宿を発見した。彼が絶対の自信を持ってそこではないと信じて疑わず探していなかった通りに彼の宿はあったということだ。
この話にはちょっとしたオチある。
彼の職業を訊くと、彼は日本で地図を製作している会社に勤めているそうだ。確かに彼は自分の宿のまわりのことだけは詳しく覚えていた。
草々

前略、
チェコ・スロバキアはこの年(1993年)の1月1日、ぼくが入国する4ヵ月ほど前にチェコとスロバキアに分離独立した。
ぼくはこのことを2月にパリに来るまで知らなかった。少しの間住んでいたカナダのモントリオルのアパルトマンにはテレビもなかったし、新聞もたまにしか買っておらず、ラジオは聞いていたが、FMばかりだったので報道していても理解できずに聞きのがしていたのだろう。
ぼくは分離独立直後の1月11日に、モントリオルのチェコ・スロバキアの領事館で、そのことを知らないままに査証を取っていた。
パリで分離を知り、ベルリンまで来て、この二つの国の査証がどうなっているのか不安になってきた。モントリオルで取った査証にはチェコ・スロバキアと書いてある。この査証で両方の国に入れるのだろうか。
すでにベルリンの両国の大使館は二つに分かれていた。苦労してスロバキアの大使館を探しあて、査証を見せるとそれはチェコのもので、この査証ではスロバキアには入れないというので、さらに査証を取らなければならなかった。先に取ったのと全く同じデザインのスタンプで上にボールペンで「SR」とあるのが、スロバキア共和国の印らしい。チェコの物だといわれた査証をよく見ると「CR」と書いてあった。
その後、錯綜する情報の中、結局この頃は二つの国のうちの先に入る国の査証を持っていればいいらしいということが分かったが、後の祭りでだった(どこの国でも役所の人間というのはいい加減なやつらである)。
スロバキアに入国、プレショフに到着。
宿を探そうとすると安宿の一つは満員、一つは改装中、もう一つはすでに安宿とは呼べないほど値上がりしていた。この町には他に安宿はなさそうなので、さらに移動することにした。
バスで田舎町のスピシュスケ・ポドハラディエに行った。ここは安宿だけを求めていった場所だったのだが、町の真ん中の広く小高い丘に堂々とした中世の城跡が鎮座していた。安宿のだけを求めて行ったひなびた田舎町で突如として現れた大きな城跡を見つけて、それは単にぼくが知らなかったというだけなのだが、意外な発見にとても感動した。
そこでこの城が窓から見渡せる安宿も見つかった。宿には外国人はもちろん、観光客もぼく一人のようだった。城を見に行っても、その城と周りの広い丘には自分以外の人間は全くいないようだった。
ぼくはいくらきれいな観光地でも人でいっぱいのところはあまり好きになれない。この時、この田舎町の広大な城にいるのが自分だけだと思うと、満員の観光客と分かち合うどんな美しい観光地にいる時より気分がよかった。
草々
追伸、このウェブログに載せるために昔書いたこの文章を整理していて、スピシュスキ城のことをウェブで調べていたら、いつのまにか世界遺産に指定されていたことが分かった。1993年指定ということだからぼくが訪れた少し後ということだろう。
シーズンオフだったこともあるが、ぼくが訪れたときは本当に全く観光客はおらず、観光客はおろか城跡自体が閉鎖されていて門は閉まっていて管理人すらいなかった(誰もいないことをいいことに無理矢理中に入ったりしました。失礼)。

前略、
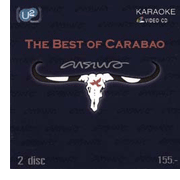
タイではVideoCDを買ってかえりました。
といっても海賊版ではなく、正規のタイの音楽VCDです。
カラバオというグループはタイではかなり有名なオヤジバンドで彼らのグループの名が冠されたドリンク剤(カラバオ・デーン)があるほどです。
ぼくは単なる短期旅行者だったので、タイやラオスでよく見たこのドリンク剤の広告のほうで彼らをおぼえていたのです(日本の薬局の前に必ずいたユンケルのタモリさんみたいなものかな)。
そんなわけで彼らの曲をよく知っているというわけではないのでとりあえずベスト盤を選びました。2枚組で30曲のビデオクリップの入ったものです(155バーツ=約430円)。
ジャケットにはKARAOKEとかいてありますが、日本でいうカラオケとはちょっと違います。
このビデオクリップには全曲ちゃんとヴォーカルが入っていて、別に消せるようになっているわけでもありません。ぼくはカラオケを全くしないので詳しいことは知りませんが、日本でカラオケというとヴォーカルはないもののことをいうのでしょう? この国には若干意味が変わって伝わっているようで画面に歌詞が出て歌えるようになっているものはKARAOKEといっていいようです。
泥臭い感じでそこがなかなかいいです。社会的な内容の歌詞も多いようです。
タイ語でさっぱり分かりませんが、カラバオのページです。
草々
前略、
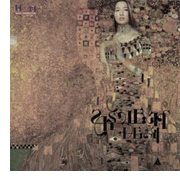
ミャンマーを旅したとき記念にミャンマーのCDを買ってかえりました。
特にこれといって知っている曲も歌手もなかったので、途中の町で音楽カセットも売っている小さな電気屋さんの女性におすすめを聞かせてもらったり、ジャケットのセンスなどでSone Thin Parの「Min Ko」というアルバムを買いました(1750チャット=約230円)。
ミャンマーではそこそこ有名な歌手のようです。若い人なら名前をいうとだいたい知っていました。
ハスキーな声で歌もうまく、適当に買ったわりには当たりでした。アメリカのポップスのミャンマー語カヴァー曲などもあって楽しいです。
この歌手の名前を最初ミャンマーで教えてもらったときには耳で聞いただけだったので「ソンデンバー」とおぼえていました。そしてそれで通じていました。
日本に帰ってからインターネットならなにか情報があるに違いないと調べはじめたのですが、「ソンデンバー」で考えられるいろいろなつづりで検索しても全くヒットしませんでした。
ジャケットの画像を見ていただければ分かりますが、そこにはミャンマー文字しかなくラテン文字でどうつづるかはさっぱり分からなかったのです。
それでもミャンマー関連のサイトを探っているうちにやっと見つけることができました。
Sone Thin Par?
かなり自分のおぼえていた発音とは違ったつづりに驚きました。
ミャンマー語のラテン文字表記の読み方が分からないので本当の名前がソンデンバーより「ソン・ティン・パー」のほうが近いのかどうかは分かりませんが、とりあえずラテン文字表記が分かりさらに調べることが可能になりました。
アルバムのタイトルが「Min Ko」であり、収録されている曲のラテン文字表記も分かってiTunesに登録することができました。
さらにうれしいのか悲しいのかちょっと微妙なのですが、ミャンマーの曲がmp3できけるサイトも見つかりました。
MyanmarMp3.net(要登録)。
Sone Thin Parをはじめいろいろなミャンマーの曲が無料で聞くことができます。ミャンマー語ラップやQueenのカヴァーなどがあってなかなか楽しいですよ。
草々
リガを出発、エストニアに入る。
タリンは三国の首都の中では一番進んでいる町だった。フィンランドが海を挟んですぐ近くで、そこのテレビやラジオを常に見て聞いていたというのも関係があるらしい。エストニア語とフィン語は共にウラル語族に属していて、互いに理解し合えるほど似ているということだ。しかし、長年に渡って、自分たちと似た言語で流されてくる自国とまったく違う隣国の繁栄と発展と退廃の映像を彼らはどんな気持ちで見ていたのだろうか。
それらのお手本を長年見ていただけあって、独立後の彼らは変化も早かったようだ。独自のなかなかかっこいいファスト・フードの店がすでにあり、パスタやアイスクリームなどを売っていた。
独立後、ソ連時代は胸を出すのも御法度だったポルノもいきなり完全に解禁になり、北欧やアメリカのノーカットのポルノ雑誌を切り張りして複製しただけの雑誌が馬鹿売れしていて、ポルノ雑誌長者も出たそうだ。
三国の中では進んだ首都でありながら、タリンの旧市街はとても美しかった。小さな丘の上に立っている坂の多い旧市街はとても絵になった。
旧市街を観光中、日本人の若い旅人にあった。彼はフィンランドから船で入ってきたということだったが、彼のこの国の情報源は日本で買ったソ連のガイドブック(バルト三国が含まれている)だったので安宿の情報が全くなく、来た時は安宿をかなり探しまわったが、見つからなかったので仕方なく旧ソ連の国営ホテルだったところに大枚50ドルも払って泊まっているとのことだった。彼はその日のうちにフィンランドに帰るということだったので、ぼくが40クローニ(約360円)の宿に泊まっていることは内緒にしておいてあげた。
ぼくがこっちへ来る前に一番恐れていたのがこのことなのだ。貧乏旅人にとって「情報は金なり」なのである。
タリンからこれまで来た道を一気に南下する。
タリンからリガを通過してビリニュスへ約790キロほどの道のり。ビリニュスで一泊した後、予約してあったバスに乗り、ワルシャワへ。
深夜にワルシャワに着き、ネオンサインの輝く明るい街を見ると、最初着いたときには古くさくしょぼく見えたこの町がとても進んだ文明国の大都市に見えた。
草々
追伸、この旅は1993年のことです。


ビリニュスを深夜に出発、ラトビアの首都リガに向かう。
夜行列車のコンパートメントに入ると中は向かい合わせに2段で4つの寝台が付いたロシア式寝台車だった。寝台車に乗るのは久し振りで、高い料金を前払いしたソ連の旅以来だった。
ビリニュス駅の近くに前売り切符の専用の売り場があるということを教えてもらって、そこで1時間ほど掛かけてリガ行きの切符を買った。発券はコンピュータ化されていたが、ソ連が作ったシステムをそのまま使っているので切符にはキリル文字のロシア語が入っていた。
そこで買った切符が特に指定はしなかったのだが、寝台になっていたのだ。値段も驚くほど安く、リガまでの350キロ(東京・名古屋間ぐらい)の寝台料金が540タローナス(約130円)だった。
リガ到着。駅前のホテルへ。
部屋に入り、洗面台の蛇口をひねるとうれしいことにお湯が出た。その部屋にシャワーは付いていなかったので、受付の人にシャワー室の場所を聞くと鍵を渡された。ビリニュスの宿ではお湯が出なかったので、そこで久々のシャワーを浴びて鍵を返す。
シャワー室に鍵が掛かっているという時は、だいたいの場合、シャワーは別料金ということである。バルト三国では独立後、ロシアから輸入していた石油などの燃料が友好国価格で入らなくなったので深刻な危機に陥ったことがあった。
受付のおばさんに料金を聞くと、彼女は何か答えたが言葉が分からない。ぼくが理解してないと分かると、彼女は片手の指を一本立て、もう片方を全部開いて並べて見せた。この国の1ラトビア・ルーブルは約1円である。
1本と5本。15ルーブルか、60ルーブルか、まさか150ルーブルということはないだろう。
分からないので、紙に書いてもらうと、そこにはしっかりと「6」とだけ書かれていた。6円だ。
ちなみに宿代には白黒テレビ代として5ルーブルが含まれていた。
ちなみに、日本人は6から9の数字を手で表す時、開いた掌の上に立てた指を置いて示すことが多いが、このやりかたでは外国人に分かってもらえないことがよくあった。例えば「6」を示すのに、開いた掌の上に1本立てた指を置くと、開いた掌を単なる背景と見なして「1」だと思われてしまうのだ。
ビリニュスは田舎という感じだったが、リガはそれに比べるとかなり都会だった。ロシア系が三国の中で一番多い(約3分の1)というのが関係あるのかは分からないが、新市街は堂々としたモスクワのような印象のある街だった。



つづく
ワルシャワをバスで出発する。
夕方の6時頃、国境に到着。出国を待っている長いトラックや乗用車の列の横を通り抜けて止まると、ポーランドの出国審査のために制服をきっちりと着た中年の無表情な係官が入ってきた。ぼく以外の乗客はすべてポーランド人とバルト三国の人のようだ。彼らに対する旅券のチェックは簡単なものだった。
しかし、ぼくの番になって無表情の係官は、人が変わったようにぼくの旅券を調べ始めた。無言のまま、すべてのページをたっぷり5分間は前へ後ろへと繰りながら、他の国の査証のページも穴の開くほど調べていた。その真剣な表情は単に好奇心から見ているとはとても思えず、どこからか何でもいいからミスを捻り出して金でもせびろうとしているように見えた。
結局、彼はぼくの旅券から何も見つけだせなかったらしく出国スタンプが押され、彼は無言のまま旅券を突き返してきた。
しばらくして、今度は帽子を斜めにかぶり制服のボタンも留めずに着くずした若い男が入ってきた。リトアニアの係官だった。彼は乗客と陽気に話しながらチェックを進め、ぼくの旅券を見ると、「ジャパーン!」と大袈裟に叫び、ぼくになにごとか話しかけてきたが、それはエストニア語だったようだ。彼がぼくに何か尋ねると乗客はそれを聞いて笑っていた。
彼はすべての乗客の審査を終えると出ていった。彼はぼくの旅券に入国スタンプを押すどころか(スタンプを持ってなかった)、査証も調べず、表紙を見ただけで旅券を開くこともなく出ていった。
後ろの席の英語を話す女の子に、彼がぼくにした質問のことを尋ねた。
「彼はあなたに『拳銃は持ってないね?』って尋ねたのよ」
リトアニアはとてもいいところのようだ。
夜の10時にリトアニアの首都ビリニュスの元ソ連の国営高級ホテルだったホテル・リトバ前に到着した。
ワルシャワからここまでは列車でも来れる。夜行の直通列車もあるのだが、これを使うにはとても大きな問題があった。ワルシャワからビリニュスへの直通列車は、ポーランドから直接リトアニアに入らずにバルト三国と同じく元ソ連の共和国で独立したベラルーシの領土の北西部の隅をほんの少しかすめていくために、ソ連時代は何の問題もなかったのだが、今ではベラルーシの通過査証が別に必要なのである。
ぼくがワルシャワで情報を聞いた中の一人は、これを知らずにこの列車に乗ってしまい、列車がポーランドを出てベラルーシに入り入国審査官が来た時、彼はそこがベラルーシであることを知らないので、最初、状況が全く把握できなかったらしい。やがて、そこがベラルーシであることが分かったが、後の祭り。彼はほんの少しその国を通るためだけに査証代を数十ドル請求された。彼はなんとか払わずに済むように交渉したらしいが、その列車がベラルーシを通ることを知らずにくる旅人は多いのだろう、向こうは慣れたものだったらしい。
「別に我々は君をポーランドに送り返してもいいんだよ」
そういわれて、彼は査証代を払うしかなかったそうだ。
リトアニアに着いてから知ったのだが、この時にはソ連時代には廃止されていたポーランドとリトアニアを直接結ぶ路線が再開されていたらしい。
宿を探しに行く。ワルシャワで聞いた情報に従っていくと、そこは普通のアパートメントのようだったが、受付のおばさんに話すと泊まれるということだった。部屋がたくさん空いているので、多分、内緒で旅人に部屋を貸しているのだろう。通された部屋は狭いワンルームの部屋でアパートメントなのでキッチンとバスルームが付いていたが、お湯は出なかった。宿代はドル払いで4ドル(帰りにもう一度泊まった時は2ドル)だった。
一休みした後、街へ出て10ドル両替した。ロシアの貨幣であるルーブルもまだ多少流通していて使われていた。
ビリニュスの街には高層建築は全くなく、高い建物はすべて教会という古い落ち着いた町並みが続いていた。ビリニュスはこれまで訪れた国の中で最もなにもないいなかな首都だった(この後に訪れた国も含めても第1位は変わらない。つまりラオスのビエンチャンよりもいなかということ)。
この後のバルトの国もそうだったが、街にはたくさんの花屋があり、これらの国の美しいアクセントになっていて、心を落ち着かせてくれる。
近くのセルフサーヴィスのカフェで食事をした。コーヒー、ゆで卵、茹でたソーセージを食べて、150タローナス(40円弱)。この調子では宿代はドルで払っているし、数日ではとても10ドル分を使い切れそうにないので、まずかなり伸びていた髪を切りにいったら300タローナス(80円弱)、そこでこの夜はワルシャワで教えてもらった高級レストランに行って食事をした。ピンク色のグランド・ピアノがあって(演奏はしていなかった)正装したウェイターのいるところである。
ボルシチ、キエフ風カツレツ(レーズンとバターの入ったチキンのカツレツ)、アイスクリーム、紅茶で、たったの760タローナス(200円弱)。安いのはとてもいいのだが、一人で食事するのにジーパンと汚れたジャケットでいちいち高級レストランに入るのは気詰まりだった。しかし、ビリニュスにはまともなレストランのほかにはセルフサーヴィスのカフェぐらいしかなく、気軽に入れるレストランがあまりないのだ。まだあまり外食の習慣がないのだろう。


つづく
前略、
バルト三国には独立の頃から注目していた。旅人は新しく独立した国や個人旅行が解放された国などがあると行ってみたくなるものなのである。
今回も東欧に行くと決めた時、できればバルト三国に寄りたいと思ったのだが、カナダを出た時点では計画は全く具体的ではなくほとんどあきらめていた状態だった。問題は情報の少なさで、カナダを出発する直前にでたガイドブックにやっと少し情報が載り始めたというところだった。
多少情報が少なくても、治安さえ問題なければ、だいたいはなんとかなるものなのだが、今回、ぼくはほとんど必要最小限と思われる資金しか持ってきていなかったので、不必要な浪費は押さえなければならなかった。バルト三国の物価が安いであろうということは容易に推定できたが、国によってはいくら一般の物価が安くても、すべてのものが安いとは限らず大きな出費がかさむことがある。
その代表的なものが宿泊費で、特に共産圏では外貨を稼ぐため、旅行者に国営のデラックスなホテル以外には泊まらせなかったり、そこまでいかなくても一般市民が使う安宿には泊まれなかったりする場合が多い。宿泊施設自体も少なくて、ドミトリー形式などという薄利多売の資本主義的なシステムがほとんどないため、宿代が結構掛かってしまう場合が多いのである。
前回の旅では、中国からバルト三国も所属していてまだ崩壊していなかったソビエト連邦をシベリア横断急行で通り、フィンランドに入った。ソ連ではイルクーツクとモスクワのホテルに1泊ずつしただけ(あとは寝台列車泊)だったが、それぞれ1泊が約70ドルと140ドルの高級ホテルを予約して日本で前払いする必要があった(当時のレートは約135円)。これらはソ連の一般市民の月給より多かっただろう。
ホテルだけではなく、ソ連では国内旅行のすべての予定を出発前に決めて、すべての宿泊と移動(列車、飛行機)の予約をして、料金を前払いしないと入国査証が出ないシステムになっていた(トランジット・ヴィザの場合は予約しなくても出る)。
その後、バルト三国は独立してこのソ連式の査証システムがなくなったことは分かっていたが、安宿がある可能性はまだ低かったのでバルト行きはほとんどあきらめていた。しかし、ポーランドのワルシャワまで来て少しずつ情報が入り始めた。
ワルシャワのユース・ホステルに着くと、これからバルト三国へ行くという白人の女の子がいた。彼女に聞いてワルシャワにリトアニア大使館のあることや、首都のビリニュス行きの長距離バスがあることを知った。でも、彼女は安宿の情報は知らなかった。
ユース・ホステルの掲示板を見ると、リトアニア大使館の住所に加えて、日本人は査証を無料で取れるという日本人のメッセージとバルト三国はそのうちの一ヵ国の査証ですべてに通用することなどが書かれていた。
それらの情報を得た次の日、宿の情報は相変わらずなかったが、とりあえず大使館に行き査証を申請し、バスのスケジュールや料金も聞きにいった。この時点ではまだ行くとは決めてなかったが、査証は無料なので行けなくても記念になるだろうと思ったのだ。
その次の日、ついにユース・ホステルにバルト帰りの旅人が別々に二人もやってきた。彼らが苦労して探した安宿などの情報を教えてもらい、バルト行きはついに決まった。

つづく
前略、
ビリー・レッツが好きです。
ビリー・レッツはアメリカの小説家でいままでに2冊の長編小説を出していて、両方とも翻訳が出ています。
「ビート・オブ・ハート」Where the Heart Is ★★★★★
妊娠したティーンの女の子が恋人と新天地を求めて西海岸へのドライブ中、ささいなことから田舎町のマーケットに置き去りにされてしまう。全くお金のないその娘は毎晩マーケットに忍び込んで夜を明かしていたが、ある夜産気づいてそこで出産してしまう。
幸せではなかった女の子はその田舎町で人々の優しさに触れ、新たな人生を歩みはじめる。
この小説はナタリー・ポートマン主演で映画化され「あなたのために」という邦題で公開されましたが、ぼくはまだ見ていません。イメージをこわされるような気がするので。
「ハートブレイク・カフェ」The Honk and Holler Opening Soon ★★★★★
田舎町の小さなドライヴイン・カフェを営む30台の男。家族同然の中年女性のウェイトレスはいるが、コックは何度雇っても長くいついたためしがない。
ある日、けがをした犬を抱いたネイティヴ・アメリカンの若い女がヒッチハイクで店にやって来る。女はバイトでカー・ホップ(ドライヴインの車相手のウェイトレス)をやらせてくれとたのんでくる。中年女性は「この女はトラブルを招く」と感じる。
こちらも映画化されるようで、レッツ自身が脚本を担当したとも聞いているので、多少期待が持てますが、主演がまたナタリー・ポートマンという噂も聞いていて原作のインディアンという設定を替えてしまっているのかが気になるところです。
最初に読んだのが「ハートブレイク・カフェ」のほうで、読み出したらやめられなかった上に、読み終わった直後からまた最初から読みはじめたほどです。
レッツの作品はダサいいいかたでいうと「癒し系」、傷ついて不幸な人たちがまわりの人々(彼らも決して幸福というわけではない)のやさしさに触れ、前向きに進んでいこうとするというような話です。ウィーピー(お涙頂戴もの)だともいわれますが、ぼくはあまり行き過ぎていなければウィーピーなのも嫌いではありません。
新作の「Shoot the Moon」がアメリカで発売されています。ほしいのですが、ハードカヴァーなのでちょっと高くて躊躇しています。
草々






前略、
宿でアメリカ人の女の子と話していた時、ぼくが日本を出て1年ほど経つと話すと、彼女はホームシックにならないかと尋ねてきた。ぼくはホームシックにはならないが、日本食がとても食べたいと答えると、彼女はそれに大きくうなずいてこう言った。
「そうね、私もアメリカ料理がすごく食べたいわ!」
アメリカ料理…? ぼくは彼女の意表を突く答えに一瞬言葉を失った。しかし、日本人が日本食を食べたいのだから、アメリカ人がアメリカ料理を食べたいというのも当然ではある。それは分かるのだけど…。
ぼくは好奇心を押さえ切れず、彼女にどんなアメリカ料理が食べたいのか尋ねた。
「リアル・ハンバーガー!」
彼女は堂々とそう答えた。
彼女にとって、ポーランドのハンバーガーやマクドナルドは「リアル」ではないのだろう。彼女が「リアル」と強調するところに自国の食文化に対するこだわりが見えなくもないが、こだわる対象がハンバーガーになってしまうところにその違いが見えた。
ちなみに、そんなことを考えていた食の国、日本からの旅人であるぼくの食べたかった日本食は「リアル・コロッケ!」だった。
草々
前略、
短い間だが、モントリオールにアパルトマンを借りて住んでいた。
カナダの大都市には必ず中華街があって、ヴァンクーヴァやトロントの中華街はかなりの大きさだが、モントリオルのものはフランス語圏の州ということでか規模は小さい。そのいつでもごちゃごちゃと人の多い中華街にはもちろん中国系の移民たちがいる。
カナダには中国系の他にもたくさんの移民がいる。ぼくの住んでいたアパルトマンの管理人はインド系、同じ階の学生はスーダンからの私費留学生で、留学を終えたらそのままカナダに住みたいといっていた。世界各国の料理がファスト・フードで食べられるのも、移民がそれだけ多いということだろう。
モントリオールはフランス系という理由で移民の数は他の州に比べると少ないのかもしれないが、それでもよく目に付く。最近は移民の受け入れに消極的になってきているアメリカに変わって、カナダは大きな受け入れ先になっているのだ。
カナダへの移民が多いのはやはり香港からだろう。
街を歩いていても中国系は東洋人ということもあり、移民の中ではよく目立つ。彼らのファッションなどは全く垢抜けてるので、日本人とは一見して見分けが付かないのだが、よく見ているとなんとなく分かる気がする。簡単にいって、日本人のほうが幸せそうな顔をしているのである。ある日本人の旅人は、同じことを「日本人はへらへらとしてるからすぐ分かる」と悪意を込めて表現していた。
遊びに海外旅行に来ている日本人が「へらへら」と幸せそうにしているのは当たり前ともいえるが、それを抜きにしても中国系の人々の表情は概して堅い。
もともと、漢民族はそういう顔なのだといわれればそれまでだが、大きな異文化の中に入った少数派であることがそうさせるのかもしれない。
ハリファクスの鉄道の駅で会って、しばらく話をした移民8年目という初老の中国系のおじさんは、「この国には人種差別がある」、「自分はこの国に来てからいいことが全くない」と、ぼくにそういった。
モントリオルのユース・ホステルで、移民先を探しているところだという若い男に会ったこともある。彼のこれまでの生い立ちは複雑だった。
彼はイスラエル人ということだったが、生まれはそこではない。彼はロシアで生まれたユダヤ系のロシア人なのだが、当時のソ連を離れ、一旦は難民の査証を得てアメリカに住んでいて、後にイスラエルに帰化したのだ。
やっと安住の地を見つけて落着かと思われたのだが、旅での出会いが彼の行く道をまた複雑にした。彼は旅の途中で出会ったベルギーの女性と恋に落ち、結婚する。詳しくは教えてくれなかったが、ロマンチックな話もあったと笑っていた。
二人は結婚後、ベルギーに住み、赤ちゃんも生まれた。幸せな生活ではあったが、問題もあった。彼の奥さんが生まれ育ったのはベルギーのフランス語圏(ベルギーもフランス語とフラマン語の二つの公用語を持つ国である)で、話せる言葉はフランス語と英語で、クリスチャンである。彼のほうが話せるのはロシア語と英語とヘブライ語(イスラエルの公用語)がいくらか、というわけで、彼ら夫婦は英語で話している。
彼によると、ユダヤ人でないものがイスラエルに住むのはかなり厳しいという。ベルギーに住むなら、彼は子供のことも考えて、彼にとって4ヵ国語目になるフランス語を勉強しなければならないだろうという。そこで彼らは、全くの第三国に移民する可能性を探っていたのだった。そのため、二人の共通語である英語と彼女の母国語のフランス語が公用語で、しかも移民の受け入れに寛容なカナダに来たというわけだった。
ちなみに、カナダでは四年間のうちに合法的に三年在住していれば、帰化を申請することができるそうだ。また、カナダは国籍に関して生地主義を採っているので、カナダで生まれた赤ちゃんは両親の国籍には関係なくカナダ国籍が与えられる。
ロッキーを旅している時にも、それぞれ別の国から海外旅行でカナダに来ていて、カルガリーのユース・ホステルで知り合って結婚し、カナダに住んでいるという家族にあったが、二人の間に生まれた子供はカナダ国籍だが、カナダに帰化していない夫婦は元の国籍のままなので彼らは家族全員の国籍が違うのだった。
[写真はモントリオールではなく、同じケベック州のケベック・シティ]
草々



