前略、

4月28と29日に六本木ヒルズで「スーパー・クリエイターズ・アリーナ2」というクリエイターやアーティストが集まってフリー・マーケットをやるイベントがあった。
旅の知り合いがメンバーであるデザイン・ユニットの大日本タイポ組合が参加するというので見に行った。
着くと、いきなりステージでタイポ組合がライヴペインティングをしていた。「祝」という字の形で「ライブペインティング」と読めるデザイン。
彼らの次に、ソラミミスト安斎肇さん登場。ポスカでイラストを描く。30分ほどで完成。塗りつぶしてしまうつもりかと思った。
フリー・マーケットにはたくさんのデザイナー、写真家、イラストレーター、画家などが店を出していた。
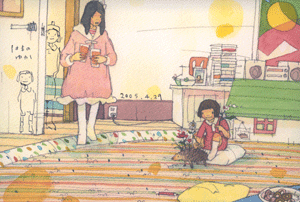
イラストレーターのはまのゆかさんのブースでポストカードを買って、直筆のイラストとサインをしてもらった(ドアのところに黒のペンで書いてあるのが直筆)。はまのゆかさんは村上龍さんの本の表紙のイラストをたくさん描いている…のだが、ぼくは村上龍には興味がないのでこのときは知らなかった。
草々
電気のない旅はいい。
電気がなければ、テレビもカラオケもインターネットもなく、しずかなひとときが過ごせる。ミャンマーでは坊さんが、右翼の街頭宣伝車のようにスピーカーで説法を大音量でがんがん流すところがあるが、停電になればこれも止む。
実際には静かに過ごすにはさらにいくつか条件が必要だ。日常的に停電のある場所の宿やレストラン、商店の一部はエンジン式の発電機を置いていて、停電するといっせいにエンジンが動き出して逆にうるさくなる場合がある。ミャンマーなどの車の多い国だとかなり田舎へ逃げる必要がありそうだ。
電気がないのがいいなんていっているのは、一時的に滞在する旅人の勝手な意見だと思う。ラオスのデット島で泊まった宿の二十三歳の娘さんは、その電気もほとんどなく、車も水道もない、テレビもカラオケもインターネットもない(ラジオはあった)、メコン川に浸かって体を洗う島に生まれ育った。雨季にはメコン川の水量が増え日常的に床下浸水状態になり泊まり客も来なくなると話していた。
都会から短期間来た旅人がお気楽に「いいところだ」と繰り返すと、けなされるよりはましでも、複雑な気持ちかもしれない。
一時的にでもそんな旅をしているうちに、ぼくの日本での生活も少しだけ変わってきた。
昔に比べるとぼくの生活はシンプルになった。昔はいろんなものをため込んで持っていたのだが、背中に背負えるものだけで何年も生活できることが分かってからは、なるべく物を持たないようにしようとするようになった。
一番分かりやすい変化は、テレビを見なくなったということだろうか。昔はテレビやビデオが好きで録画した映画やテレビのテープ(ベータ方式!)が山のようにあったのだが、テレビのない生活を始めて十年近くになる。
テレビを見てないとテレビドラマやコマーシャルの話題には入れないし、アイドルやお笑いタレントの顔と名前が一致しなくなるし、年末の「今年の流行語」なんてものも半分以上は初めて聞く言葉だったりする(ギター侍ってなに?)。
でもテレビがなければ、テレビ番組表やビデオ録画などというものにわずらわされず、液晶テレビ、プラズマテレビ、DVD、HDDビデオデッキなどという製品にも無関係でいられる。地上波デジタル放送? どうぞご勝手に、という感じだ。無意味にテレビを見ていた時間が自分の時間として使える。
なかでも最大の利点を教えよう。
NHKの集金人が来た時に、何の後ろ暗いところもなく、絶対の自信を持って、「見てない! 失せろ! おとといきやがれ!」と言えるのだ(集金人はテレビのないことを信用してないようだが…)。
でも、日本で電気のない生活をするのはかなり難しそうだ。
草々
(「野宿野郎」2号より転載)
ラオスやミャンマーでも停電の多い町は多かった。
ラオスでは石油はほとんど産出せず、発電のかなりの部分を水力発電で行っている。ミャンマーは産油国なので火力発電が盛んだが、水力発電にも力を入れており、電力の数割は水力で行っている。
水力発電は雨季のあいだはいい調子なのだが、乾期に入り、川の水量が減りだすと発電量も減るので乾期の終わりになると停電が多くなるらしい。ラオスが水力発電で作った電気を隣国のタイに売っているというのは有名な話だが、自国で余った分を売っているというより売れるものがほかにはあまりないので自国で必要な分も売っているということらしい。
ミャンマーでは、首都のヤンゴンはたまに停電があるくらいだったが、地方に行くと停電が多くなり、週に三、四日だけ電気が来るというところもあった。
ラオスの北部ノンキャウという田舎の村では電気が来るのは日没から三時間ほどだけだった。村の一本だけのメインストリートを電気のなくなったあと歩いていたら道の真ん中で寝ころんでいた犬のしっぽを踏んでしまったほどだ。しかし、日本からきたぼくには全くの暗闇でも地元の人にはそうではないらしい。ある夜、小さな懐中電灯で暗闇をおそるおそる歩いていると、暗闇の中からぼくに話しかけてくる声があった。声のするほうを向いても暗闇しか見えず、しばらく懐中電灯でさがすと知り合いになったラオス人がなにも持たずに真っ暗な中を歩いてくるのが見えた。
ラオスの南部、カンボジアとの国境近くのメコン川の中にシーパンドン(四千の島)と呼ばれる小さな島々がある。関係はないが、ドレッシングの名前で有名なサウザンド・アイランド(千の島)はカナダのセント・ローレンス川の中にある。
そのシーパンドンの中のひとつであるデット島に滞在した時も電気は限られたもので、ぼくの泊まった宿には電気が引かれてなかった。
島のふちは一、二メートルのでこぼこの未舗装の道になっていて、その外側はそのまま数メートルのがけになっていてメコン川に落ちている。街灯などはもちろんなく、小舟で行き来するだけの島なのでトラクターが数台あるだけで車は全くなく、日が落ちるとほぼ真っ暗闇だった。
ただの真っ暗な村なら歩いていても、こけるか、ぶつかるか、犬のしっぽを踏むかぐらいで命にかかわることはないのだが、そこはそうではなかった。明かりを持たずに外に出て、日が暮れてしまうと、足を踏み外して崖下のメコン川に転げ落ちる危険があるのだ(実際に落ちる旅行者もいると聞いた)。
ある日、真っ暗な中を懐中電灯を持ち、またおそるおそる歩いて細い道を宿に帰ろうとしていたら、いきなり目の前で甲高い金属音がして、ぼくは声を上げて驚いてしまった。目の前には笑っている地元の島民が自転車に乗って止まっていた。もちろん自転車にライトなどは付いていない。もうびっくりである。道の一方は崖になってメコン川に落ちているでこぼこのほとんど真っ暗な道で、ぼくなら懐中電灯がなければ四つんばいになって這っていかなければ前に進めないようなところを平気で自転車に乗っているのだから。でも、むこうにしてみればちゃんと見えているから自転車に乗っているわけで、こっちから見えているのだから、向こうもこっちのことも見えて当然だと思っていて、何であの外国人は自転車がきているのによけないんだと不思議に思っているかもしれない。
つづく
中東を廻っていたとき、ヨルダンからシリアに入ってダマスカスの宿でのこと、ぼくの訪れた安宿にはあまり空き部屋が残っておらず、安いが窓がないという部屋に通された。ダマスカスにはそれほど長く泊まる予定でもなかったのでそこに決めて、昼間から電気をつけて荷をほどいて休んでいると、突然停電した。このあたりでは停電は珍しくないし、宿のヒューズがとんでしまうこともある。
話が少し脱線するが、ぼく自身が宿のヒューズをとばしてしまったことも一度や二度ではない。ぼくは旅に必ずコイル・ヒーターなどと呼ばれているコンセントにつなぎ、ヒーター部分をコップの水に突っ込むとお湯が沸かせる器具を持っていく。これがあれば電源と水道さえあればどこでもお湯ができ、コーヒーや紅茶、インスタントラーメンやみそ汁などが飲めるので、ぼくの旅には欠かせない道具になっている。
旅に出た先で買えば値段は安いし、便利この上ないのだが、作りが雑なものが多く、使っているうちにヒーターのコイル内部に水が入り込んで漏電するようになってくるものがある。湯を沸かしているときにコップの取っ手を握ったら電気で手がしびれたこともあった。そして、ある日突然、壊れて湯を沸かせなくなってしまうのだが、この時、電気がショートしてしまって宿のヒューズをとばしてしまうことがしばしばあるのだ。自分の部屋のヒューズをとばすぐらいならたいしたことはないのだが、場合によっては宿中が停電してしまったりすることもあって大変ばつが悪い(でも知らんふりをする)。途上国では日本のようにすぐ元に戻せるブレーカーではなく、文字通りヒューズを使っているので直すのに手間と時間がかかるのだ(もうヒューズなんか知らない人も多いかもしれないので説明すると、ヒューズというのは電気を通す金属で過剰な電流が流れると溶けて電気を遮断する。なので溶けてしまうと新しいものに付け替えなければならない)。
一度など、宿のロビーで湯を沸かしていたらコイルヒーターがものすごい火花をあげて小爆発を起こし宿を停電させてしまったことがあった。
話を戻すと、この時のダマスカスの宿の停電は真っ暗な部屋でしばらく待っていてもなかなか復旧しなかった。宿のオヤジさんに訊ねると、そこでは十四時から十八時まで毎日停電するということだった。
シリアはアラブの国にもかかわらずアラーの贈り物である石油がほとんど産出しないために慢性のエネルギー不足で、水不足の時に断水をするように、一日のうちの一定の時間「断電」をしているのだった。
ダマスカスの後、パルミラへ足を伸ばした。
パルミラは砂漠の中のオアシスにあり、紀元前後にシルクロードの隊商都市として栄えたが、後にローマ帝国に滅ぼされ、ギリシャ・ローマ文化に影響を受けた神殿や劇場などの遺跡が残っている。
この町でもしょっちゅう停電が起こっていたが、定期的なものではなかった。ある日、日の高いうちに始まった停電は日が暮れたあともつづいた。部屋にいてもしょうがないので夕方、寝袋を持って屋上で寝ころんでいた。空が暗くなるにつれ星が瞬きはじめた。この町は砂漠の中のオアシスの町なのでまわりに空気をよどませるものはなにもなく、乾燥しきっているので雲も全くない、都会で星を見えにくくしている要因のひとつである町の明かりも停電のために(全くというわけではないのだが)ない。
空には満天の星が広がっていった。日本の都会で見る何百倍、何千倍の星だろう。天の川がはっきりと帯状に見えた。星くずとはよくいったものだ。星が多すぎて漆黒の空にほこりを散らして汚れているようにも見えた。
つづく
前略、
電気のない旅が楽しくなってきた。
最初に電気のない旅を経験したのはカナダだっただろうか。カナディアン・ロッキーの南の入り口の町のバンフまで来て、その場の思いつきで自転車を買ってロッキー山脈を縦走してみた。山脈を縦走するといってもそこにはちゃんとした舗装道路(ひび割れだらけだけれども)が通っていて、車や観光バスだと半日で通り過ぎてしまうところである。いろいろ調べてみるとロッキーの道路沿いには数十キロごとにユース・ホステルがあるので、自転車さえあればテントや調理道具などの重装備をする必要がなく、バスで半日で観光して通り過ぎてしまうよりじっくり楽しめると思ったのだ。
山に入って最初のうちはユース・ホステルも町と変わらない設備だったのだが、国立公園内に入っていくと開発の制限があるので宿は山小屋風で設備は最低限のものになり、水道も電気も電話もなくなった。
調理はプロパンガス、照明はガスかオイルランプ、暖房はガスや薪、飲料水は近くの小川からポリタンクで汲んできて五分間ほど煮沸消毒する。小川の水はロッキーの雪解け水なので冷たく澄んでいて、一見何の問題もなさそうなのだが、ビーヴァーのおしっこに含まれる成分でかかるというビーヴァー・フィーヴァーという熱病になることがあるらしい。
あるユース・ホステルには冷蔵庫があったので驚いた。電気のない宿にある冷蔵庫なのに開けるとちゃんと冷えていた。よくみるとガス管がつながっていて、ガス冷房という仕組みがあるとはしらなかった当時はふしぎに思ったものだった。
別のユース・ホステルではお客が宿泊料をクレジット・カードで払っていた。電気も水道も電話もなく、トイレも離れの個室で穴の中にするような一泊八ドルほどの宿でも、さすがはクレジット社会の北米なのである。
舗装道路が通ってはいるものの、やはり山の中を自転車で行くのは坂道がかなりきつく、途中の宿では雪に降りこめられてなかなか出発できなかったり、食料が足りなくなって団体客(自転車で旅するツアー客がいた)にめぐんでもらったりして大変だったが、雪山や川、湖、大氷河は美しく、鹿やビッグ・ホーン・シープ、マウンテン・ゴート、黒熊、グリズリー・ベアーなど野生動物も見れて、バスで半日で通り過ぎるよりはよっぽど楽しい経験ができた。
つづく
前略、

旅人としては手回し充電の商品は気になるところ。以前からこの手のラジオはあったが、でかくて高かったので旅向きではなかった。東芝のこの商品(TY-JR10)は小さいし、LEDのフラッシュライトがついていたり、軽い防水仕様になっていたりと、かなり旅に向いている。
とはいうものの、なかなか購入に踏み切れない点もある。
まずFMがモノラルというのはちょっとマイナス。5000円という値段もちょっと高い。
そしてこの商品の売りのひとつである携帯電話の充電機能というのがぼくには不要なもので、もしこれがiPodの充電にも対応してくれていたりすると、即購入となるのだが。
これだけiPod関連商品があって、乾電池式のバッテリーパックや車載ユニットや太陽電池式の充電ユニット(「Solio」)はでていても、手回し式はまだないようだ。どこか作らないかな。
草々

前略、
散髪はいやだ。というのはぼくが小学生の時に書いた作文の中で唯一教師に評価されたものだ(なぜ評価されたかは今も分からない)。
子供のころは父がバリカンとはさみで刈ってくれていた。その後、散髪屋や美容院に行くようになったが、今も髪を切ることがいやであることには変わりない。
そして、以前から興味を持っていたが、なかなか実行に移せなかった「マイ・バリカン」を買うという計画を実行に移した。
ナショナルの「カットモード」。水洗いできる電気バリカンだ。
バリエーションがいくつかあるのだが、みたところ髪を刈る長さを調節するアタッチメントが違うだけのようなので、もっともシンプルで安い「ER504P」にした。値段は1〜2回分の散髪代しかしないのだから、安いものだ。
それからは髪は家で自分で刈っている。自分一人で刈る場合は、いくらアタッチメントが付いていても後頭を調節するのはかなり難しいので、ぼくはもうボーズにすることにした。
自分で散髪すると、散髪がいやではなくなった。
散髪がいやなのではなく、刃物を持った他人に自分をいじられ、コントロールができないことがいやだったのだ。
草々
追伸、バリカンの語源に興味のある方はこちらの記事をどうぞ。
前略、
今日、電車に乗っていたら和服を着たおばあさんがいた。おばあさんといってもそれほど年寄りではなく六十代くらいかな。
そのおばあさんは白いイアフォンしていた。
おっ、その白いイアフォン、そして、その白いコードの先につながって手に持っているものは、ひょっとして…?
おおっ、アイポッド・シャッフルじゃないですか。
ハイカラ〜!
じろじろ見るわけにもいかないので、よそを見ていましたが、電車から降りようとしているおばあさんをもう一度見た時には、おばあさんのアイポッド・シャッフルは和服の胸元、衿の合わせのところにきゅっとはさんでありました。
いかす〜!
ひょっとして、「コンピューターおばあちゃん」?
軽くて小さいアイポッド・シャッフルならではの和服装着法、そして真っ白でシンプルなアイポッド・シャッフルでなければ和服には似合わないでしょう。
おばあさんの今日のプレイリストは何だったのでしょう。
草々

前略、
「エターナル・サンシャイン」
Eternal Sunshine of the Spotless Mind
脚本:チャーリー・カウフマン
監督:ミシェル・ゴンドリー
いいね。もともとこういう構成の凝った映画は好きだ。
チャーリー・カウフマンの脚本は、観客が設定を聞いて予想するストーリーを微妙にはずし、そしてその先を行く。それでいてハリウッド式ではないかもしれないが、ストレートなラブストーリーに仕上がっている。
でも、やはりこのキャスティングは失敗だったのではないだろうか。いまやハリウッド映画はスターが出ていなければろくな予算が取れないし、ヒットしないと思われているから、大物は必要だったのだろう。比較的地味なこの作品にたくさんのスターが出ている。主役には説明の必要もないジム・キャリーにケイト・ウィンズレット、脇にカースティン・ダンスト(「スパイダーマン」)やイライジャ・ウッド(「指輪物語」)など。
脚本家や監督のインタビューを読むと、主役二人の設定は「退屈で地味でだめなおっさん」と「彼をひっぱりまわすテンションの高い若いパンク娘」だった。
ジム・キャリーはいつものハイパーテンション芸を捨ててちゃんと役になりきっているが、それでもスマートで男前すぎてだめなおっさんには見えない。
ケイト・ウィンズレットもオスカー・ノミネートもされた、こちらはハイパーテンションの切れたパンク娘を演じているが、「タイタニック」のときからいわれていた貫録ありすぎな外見で、当時29才あたりだったらしいが、おっさんと付き合ってひっかきまわす若い娘には見えなかった。ジムが若く見えすぎ、ケイトが年取って見えすぎるため、本来はアンバランスなカップルじゃないといけないはずの二人は全然お似合いなのである。
ケイトがおばさんすぎるのは、後で付き合うことになるホビット族(イライジャ・ウッド)との関係にも問題が出てくる。イライジャが子供っぽく見えるので、ケイトおばさんとのカップルが不自然なのだ。
ケイトの役はいっそのことクリニックの受付嬢役のカースティン・ダンストでもよかったくらいではないだろうか(彼女にオスカー・ノミネート級の演技ができるかは別にして)。
主役二人のかんじはちょうど「ゴースト・ワールド」のスティーヴ・ブシェミとソーラ・バーチがぴったりなのではないだろうか(あるいはスカーレット・ヨハンソンでもいけそう)。
「メメント」と二本立てで見ることをお勧めする。
草々
前略、

このビリボ、見てのとおりただのプラスチックの椅子かボールのようなもの。使い方は自由に子供に考えさせて遊ばせる玩具である。
ウェブサイトには遊びかたの例の写真がでていて楽しそうなのだが、与える子供(またはつくった親に)に創造力のかけらもないと、ただのおもちゃの入れ物となってしまうので、3000円を出して買いあたえるかはあげる子供をよく見極める必要があるかもしれない(自分の子供にあげる時はちょっとこわいだろうな)。
しかし、前に紹介した玩具「Cuboro」もスイス製だった。別にスイス製のおもちゃを探しているわけではなく、おもしろそうなのがたまたまスイス製なのだ。
スイスはおもちゃ王国、いや、おもちゃ連邦共和国なのか。

草々
前略、
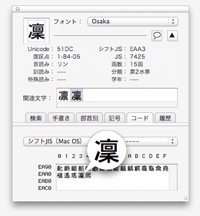
やってしまいました。グラフィック・デザイナーが最も恐れることのひとつ。
「シール貼り」の刑です(もっと恐ろしいのは「全部刷り直し」の刑ですが、幸いまだこれにはあっていません)。
同じ会社のライターが書いた原稿を元にパンフレットをデザインし、校正し、印刷が上がり、納品されました。
そこに依頼人からの恐怖の電話…。
文章の途中に突然おかしな空白がひとつ入っているという。
「…平野の中にそびえる とした姿は、…」
たしかに。
入稿したデータをチェック。
最悪! 入稿したデータも同じように空白になっている。完璧なこちらのミス。
ライターの書いた原稿を見ると、
「…平野の中にそびえる凛とした姿は、…」
と「凜」になっている。なぜ空白に。そのテキストをコピーしてDTPソフトにもう一度流し込んでみる。
げげっ!「凜」のところが空白に化けた。なぜだ!
解説しよう。なぜかというと、この時に使用した「凜」という文字はマッキントッシュのOsakaフォントをはじめ一般的なフォントにはあるが、ポストスクリプト(OCF)フォントにはないのだった。
この時に使用した「凜」という文字はシフトJISのEAA3の「凜」で、同じ読みで微妙に形の違う「凛」が997Aにもあって、この「凛」ならOCFフォントにもあるのだ。
OCFフォントにある「凛」が正字で、シフトJIS、EAA3の「凜」は異体字ということらしい。
EAA3の「凜」は異体字にもかかわらず、Mac OS 9のOsakaフォントに含まれているが、OCFのポストスクリプトフォントには入っていないのだ。
なぜわざわざこのライターは異体字を使ってきたのか。こだわりなのか。
実はこのライターは、「慣れていて他では書けない」という理由でシャープのワープロ専用機「書院」をいまだに使っており、DOS変換し、フロッピーディスクでテキストをやり取りしている。どうやら書院では「凛」の異体字が出てくるようだ。
同じようにOsakaフォントにはあるが、OCFのポストスクリプトフォントにない文字としてシフトJISのEAA4の「熙」がある。さらに付け加えれば、これらの二文字はCIDフォントには加えられたのでCIDフォントでつくればちゃんと出力される。
いや、もちろん分かっています。みなまでいうてくださるな。この事故の本当の原因はフォントがどうたらこうたらということではないのだ。
今回テキストをDTPソフトに流し込んだその瞬間から、ずーーっと、すべてのカンプや色校正でこの文章は空白が入ったままだったのだ。事故の原因はミスに誰も気がつかず、すべての校正をすり抜けて印刷され、納品されてしまったことなのだ。反省…。
草々


