二日目、コンパートメントで周さんやUさん、Kくんと話をした。昼、夜は皆で食堂車に行った。食堂車は走っている国のものが付くので料理は中華料理である。周さんにみつくろってたのんでもらった。
三日目、朝の五時に起こされた。国境が近いらしい。
国境の中国側の駅である満州里に着く。検疫が軽くあり、パスポートを持っていかれ、税関は入国時に書いた書類を持っていった。車両の入れ替えなどがあった後、駅に降りて再両替などをした。
列車に戻り、ソ連へ入国した。香港から上海へは船だったので、これが生まれて初めて地面にある国境を越える経験だった。広い草原に延々と柵が続いていたように記憶している。
島国に生まれたからだろうか。世界中のほとんどの人があたりまえに感じているであろう地面に引かれた国境にぼくは引きつけられた。一つの国を離れ、もう一つの未知の国に入るという行為は、ぼくを不安と興奮が入り混じった気分にさせた。その後、とりわけ歩いて国境を渡るチャンスがあるときは、なるべく逃さないようにするようになった。
ソ連最初の駅で制服が乗り込んできた。まずぼくらをコンパートメントから出して、中を調べ、パスポートとヴィザのチェックをした。税関は何も調べずにハンコを押しただけ。そのあいだにぼくらを乗せたまま、車両を持ち上げて車輪の台座を広軌のものに取り換えていた。
その後、駅に下ろされて再び待った。真夏だったが、ここまで北上するとかなり涼しい。しばらくすると中国のものに変わり、ソ連のディーゼル機関車にひかれた列車がやってきて出発した。
食堂車がソ連のものに変わって、ロシア料理が食べられるようになっていた。その他、途中の駅ではじゃがいものふかしたものや、ギョウザの皮にいもを包んだものなどを売っていた。じゃがいもをただふかしたものはとてもおいしくてこの列車で食べたものの中でも一番印象に残っている。
晩飯の時、ロシア人が近づいてきて言った。
「チェンジ・マネー?」
闇両替屋である。一米ドルを十四ルーブルでどうだという。当時の旅行者レートは一ルーブル二十七円ほどで、三倍ほどよかったので五ドル分両替した。
四日目、北側の車窓にバイカル湖が見えていた。昼過ぎ、イルクーツク到着。
U先生はホテルまで例の送迎車が付いているというので、ぼくたちは歩いてインツーリストホテルへ。着くと、このホテルにはハバロフスク方面からきたらしい日本人旅行者がいっぱいだった。
バウチャーを渡してチェックイン。次の日のモスクワ行きの切符は、今度はたいした手間もなく手に入った。
部屋は外国人用の高級ホテルということなのにかなりぼろかった。水道はきっちり止まらない。トイレの便座はちょうつがいが壊れている。テレビは置いてあるけど映らない。カーテンは引くとはずれる。部屋に据え付けのラジオは本体が取れてしまう。こんな部屋に日本で一万円以上払っていた。
イルクーツクの町へ出てみた。中国からやって来ると涼しいし、人は少なく、さびれた田舎町という風情で落ち着いた。
途中で闇両替屋につきまとわれた。もう列車内で済ましていて必要ないのでお断りしたが、千円で百ルーブルということだった。列車でも一ドル十四ルーブルだったので、このころの実勢レートは一ルーブル十円あたりということだったのだろう。
このころの正規の両替レートはすでに書いたように一ルーブル二十七円ほど。このレートは、この旅行を始める直前に旅行者用の特別レートとして公定レートから一気に十分の一に下がったものだった。それまでの公定レートは一ルーブル二百七十円ほどだった。さすがに実勢とそぐわないというので十分の一に下げたらしいのだが、まだ実勢レートとは三倍ほどの開きがあった。
この日の晩、列車で一緒だった日本人三人でホテルのレストランで食事を食べることになった。レストランのメニューにはルーブルで値段が書かれていたが、レートが引き下げられたばかりということもあって、過去の情報などからいろいろな不確かな情報が飛び交っていた。この時に問題になったのは、高級ホテルのレストランでは外国人に値段のルーブルを公定レートで計算して外貨払いさせられるらしい…という情報だった。
公定レートで計算されてしまうとかなりな値段になってしまうのでぼくたちはびびって三人でミンチカツと牛肉の料理を一人前とチャイ(紅茶)だけをたのんだら、結局ルーブル払いで一人二ルーブルで済んでしまいみんなで笑った(公定レートだと五百四十円、旅行者レートだと五十四円、実勢レートだと二十円)。
その他、町の喫茶店ではチャイと包子が四人で七ルーブル、露店のシシカバブが一本一ルーブルだった。
五日目、ホテルをチェックアウト。もう一晩そこに泊まるというK君のところに荷物を置かせてもらって、町をぶらぶらする。喫茶店に入り、キリル文字で書かれたメニューからコーヒーとアイスクリームとケーキともうひとつは適当に分からないけど指さしてたのんでみた。ウェイトレスの女の子はロシア語でなにかいっていたが、分からないのでそのままたのんだら、コーヒーとアイスクリームとケーキと「タバコが一箱」が出てきた。ロシアでは喫茶店のメニューにはタバコの銘柄がのっているので注意したほうがいい。
この日はバスの回数券(六カペイカの五枚つづり。百カペイカが一ルーブル)を買って適当に乗ったり、降りたりしたり、映画館へ行ってチケット(一・五ルーブル)を買ったはいいが、それが夜の回のチケットで見れずじまいだったりということをしながら時間をつぶした。ようするに観光するようなところは町なかにはなかったのだ。
夜になって駅へ。列車を待っているとホテルにたくさんいた日本人が続々とやってきた。列車が到着するとその日本人たちがみんな同じ車両だということが分かった。車両の半分以上は日本人だった。他の外国人旅行者もいたのでソ連の国際旅行社が外国人をひとつの車両に集めたようだった。
つづく
[脚注]
-
広軌
広い線路の幅の規格のこと。中国とソ連では線路の幅が違うので車両はそのままで車輪のついた台座だけを広いものに交換した。
-
ソ連のディーゼル機関車
現在ではこの路線は全線電化されているらしい。
-
ホテルまでの例の送迎車
前回参照のこと
-
公定レート
この原稿を書くためにインターネットで調べてみたところ、このころのソ連には三種類のレートが存在したらしい。公定レート(一米ドル=〇・五五四二ルーブル)、商業レート(一米ドル=一・六六二六ルーブル)、特別(旅行者)レート(一米ドル=五・五四二ルーブル)の三つ。公定レートは形骸化した名目上のもので、貿易などの経済活動には二番目の商業レートが使われた。三番目の特別(旅行者)レートというのがぼくが旅行した時期にできたもの。しかし、たいがいの旅人は闇両替していたので、公的なレートがいくらであっても関係がなかった。
-
包子
ロシアや東欧の一部では包子や餃子(ポテト入り)など中国由来の料理がその国の料理としてなじんでいる。
香港で一週間滞在し、船で上海へ、その後、北京へ。
北京でシベリア横断鉄道に乗る前の日、それまで泊まっていたバックパッカー御用達の僑園飯店から、一転、高級ホテルの前門飯店へ移動した。旅行代理店で列車に乗る前日のホテル一泊を無理矢理予約させられていたのだ。
旅行代理店でもらったバウチャーを渡してチェックインした。ホテルはバウチャーを渡せば泊まらせてもらえるが、列車はそういうわけにはいかないので、バウチャーを切符と引き換えてもらわなくてはならない。ホテルのフロントに訊ねてみたが、どうすればいいのか全く分からなかった。
ホテルを出て、別の高級ホテルである崇文門飯店の中にある中国国際旅行社まで行ってみたが、もう営業は終わったので次の日にまた来いといわれてしまった。問題は泊まっている前門飯店から北京駅までの車での送迎の予約がこれまたほしくもないのに付けられていて、この崇文門飯店が北京駅に近いところにあるということだった。このときぼくは、次の日は崇文門飯店の中国国際旅行社へ行き、切符を受け取ってそのまま北京駅に行き、送迎車なんかほっとけばいいと考えていた。
甘い、甘すぎた。中国人はそんな甘い考えはすべてお見通しで、ぼくに好きにさせてくれるはずもなかった。
翌日、シベリア横断鉄道で出発の日、ホテルで朝食を食べてチェックアウトし、荷物を持って崇文門飯店へ向かった。
中国国際旅行社でバウチャーを見せて列車の切符のことを訊ねると、いろいろと電話をかけた末に別のホテル、国際飯店の中国国際旅行社へ行けと、たらい回しされてしまった。北京駅はもう近いので、先に荷物を北京駅に預けてから国際飯店へ向かった。国際飯店に着いたときにはすでに昼時になっていて、中国国際旅行社は昼休みになっていた。
昼休みが終わったあとも窓口をたらい回しにされた後、日本語を話せる女性が出てきて、衝撃の事実を告げられた。
ぼくの列車の切符は、ぼくを前門飯店から北京駅へ送っていくことになっている車の運転手が持っているというのだ。
あほ〜! なんでそんなやつに切符を預けるのだ。素直にホテルのフロントに預けとけバカたれ! こっちはもう荷物を北京駅に預けて準備万端なのだ。また前門飯店へ戻れとでもいうのか。
再び交渉の末、七時にその運転手を今いる国際飯店に来させるということで決着した。でも、もしこれで運転手が来なかったらぼくはどうなるのだ。
恐れていたとおり、七時をすぎ、十分、二十分をすぎても運転手は現れず、ぼくはパニックにおちいったが、その直後、やっと運転手が現れた。すぐ近くの北京駅まで乗せてもらい、切符を受け取った。その時に運転手はぼくの名前ともう一人の日本人の名前を書いた紙を見せ、この日本人を知らないかとぼくに訊ねてきた。彼はその日本人も北京駅まで送り届けて切符を渡さなければならないのだが、見つからないらしい。
知るか〜! こんな駅までの送迎車を付けられたせいでこっちは大迷惑しているのだ。おまけにこんなことに金まで払ってるとか思うと、余計に腹がたつわい。
しかし、なんとか出発前に切符を持って無事、駅に着けて一安心だった。プラットフォームにはすでにソ連行き国際列車が停っていた。ロシア人の車掌に挨拶して乗り込んだ。コンパートメントは二段ベッドが二つの四人部屋。同室の中国人の周さんはソ連に招かれてモスクワまで行くとのこと。日本統治時代に日本語を習ったので少し日本語が話せた。
発車直前に外から日本語が聞こえてきた。通路に出てみると、ぼくを北京駅まで送ってくれた運転手がいて、日本人を連れていた。彼が見つからないといっていた日本人らしい。彼(K君)はホテルでいくら待っても送迎が現れずパニックになり、(多分、運転手が先に北京駅へ行ってしまったという連絡があって、)自分でタクシーを拾って飛ばしてもらい、(多分、駅で彼の切符を持った運転手に会って)なんとか間に合ったとのことだった。
これってひょっとするとぼくが送迎の運転手を国際飯店まで無理矢理来させたために起きたとばっちりだろうか。すまんと心の中だけであやまった(でも運転手に切符を預けるのが一番悪いんだからね)。
その他、高校の教師をしているという日本の女性Uさんも同じ車両だった。
ほぼ定刻に列車は北京駅を出発した。
つづく
[脚注]
-
船で上海へ
香港〜上海の客船はリーズナブルな値段で、のんびりした船の旅が楽しめたのだが、もうなくなったと聞いている。
-
僑園飯店
僑園飯店は現在もまだあるが、もうバックパッカーのたまり場ではなく、りっぱな高級ホテルになっているらしい。このころは大雨が降ると地下の安い部屋には雨水が流れ込んでたまってしまうようなところだった。
-
車での送迎
カナダのトロントのユース・ホステルに泊まっているときに、ちょっとした話題になった日本の女性がいた。その女性はユース・ホステルの前に大きな黒塗りのリムジンで乗りつけてチェックインしたというのだ。これもトロントまでの飛行機と町までの車の送迎がセットになっていて、迎えに来たのがでかいリムジンだったということらしい。
前略、
仕事を辞めて、海外旅行に出ることにした。どちらも初めての経験だった。
学生時代はお金がなく、海外旅行など考えもしなかったし、出不精なので国内旅行もあまりするほうではなかった。仕事を始めて数年経ち、多少お金が貯まったので、ここらで一度くらい海外旅行をしておこうと思ったのだった。
ある年のまだ肌寒い春先、夏には出発しようと計画を立てはじめた。
最初はヨーロッパを二、三ヵ月回って帰ろうと考えていたのだが、いろいろと調べているうちにだんだん計画は大きくなっていき、最後には、中国から北京発のシベリア横断鉄道でヨーロッパへ行き、北米に飛んでアメリカを横断して、日本に戻る西回りの世界一周旅行をしてみようということになった。
シベリア横断鉄道といえば、ロシアを走るウラジオストク〜ハバロフスク〜イルクーツク〜モスクワのルートが最も純正なものだが、他にも北京発でモンゴルのウランバートル経由のモスクワ行きと、北京からモンゴルを東によけてハルビン経由でいくモスクワ行きのルートがあり、途中から合流という形だが、これらも広義のシベリア横断鉄道とここでは呼ばせてもらう。どの列車も一度も乗り換えをすることなく運行する世界最長の路線で、そのなかでも北京発ハルビン経由は当時最も距離が長かった。
当時は日本でソ連(そう、当時はソビエト連邦がまだ存在していた)のヴィザを取るのは結構大変だった。まずソ連の国営旅行社であるインツーリストと提携している日本の旅行代理店を見つけなければならなかった。インツーリストと提携している旅行代理店と連絡を取り合いながら旅程を固めていくうちに、最初に予定していた北京発モンゴル経由の列車が団体に押さえられてしまうということがあったりしたため、ハルビン経由の列車に決め、前金五万円を払って手配を頼んだ。同時に香港行きの片道航空券の手配にもかかった。
一回目のヴィザの手続きのために大阪のソ連総領事館へ。
もちろん旅行代理店にお金を払えばヴィザの手続きなどはすべてやってくれるのだが、ぼくは計画や手配も旅の楽しみのうちだと思っているので、個人でできるのであれば、できるだけ自分で行って手続きするということにしていた。
大阪のソ連総領事館は大阪市内ではなくちょっと辺鄙なところにあった。駅のインフォメーションが領事館のある豊中市の西緑ケ丘と池田市の緑ケ丘を混同したため乗り越してしまい、歩いて戻ろうとしてさらに道に迷い、交番で訊ねたり、人に訊いたりして、なんとかたどりつくことができた。
領事館の手前には「こちら豊中市ソビエト連邦総領事館前派出所」とぼくが勝手に呼ぶようになった交番があり、ぼくが交番に気付いたときには、警官が出てきてこちらをじっと観察していた。近づくと警官は「総領事館ですか?」「ヴィザですか?」と訊ねてきた。総領事館の入り口はまだその少し先の方なのにどうしてぼくの行き先がそこだと分かるのだろう。警官は慇懃にぼくを総領事館の入り口まで誘導しドアまで開けてくれた。
総領事館に入ると高い天井に赤い絨毯。廊下の突き当たりにはレーニンの胸像があった。受付にヴィザを取りにきたと告げると、日本語が話せるロシア人の担当の人が現れ、個室に案内されてソ連旅行の旅程などに関するアンケート用紙に書き込んだ。
アンケートを書きながら思った。なんでソビエト連邦総領事館前派出所の警官は、ぼくが総領事館に用があると分かったのだろうか。道に迷ったときに別の交番で総領事館への道を訊ねたのだが、そこから総領事館前派出所に人相、風体などの連絡でもあったのではないかと思って、気味が悪くなった。
アンケートを書いていて、記入に必要な旅行代理店にもらった資料を忘れたことに気付いた。ロビーにあるピンク電話から旅行代理店に電話をかけることにした。
受話器を上げてお金を入れても何の音もしなかった。もう一度試すと今度は通じた。
旅行代理店の女性に必要なことを訊ねていると、ノイズの交じる音でその女性は言った。
「電話が遠いんですけど…」
ロビーにある冷水器は壊れていて水が出なかったし、トイレの水道は出が悪かったのだから電話の接続がおかしくても不思議ではないが、もし盗聴しているんだったら、もっとうまくやれと心の中で毒づいた。
個室に戻ってアンケートのつづきを書く。アンケートを書いているテーブルの隅には「SDIは核を無力化できるか」という日本語の本が置いてあった。
高い壁の天井に接して小さな窓が並んで付いていた。こちらから外は全く見えない。外からも覗けない。
アンケートを全部書き込み、ヴィザ代千円を払い込んで最初の訪問は終了した。
数日後、旅行代理店から見積額が届いた。十三万円強。高いなぁ。
さらにひと月ほどたって、すべての予約が入ったとの連絡があった。前後して、香港行きの片道航空券も手配が完了した。
その後、旅行代理店からバウチャーとテレックスの用意ができたと連絡があった。
バウチャーとはソ連国営旅行社が発行する旅行の予約引換券のようなもので、旅行者が旅に持参して、ホテルに泊まるときに渡したり、列車の切符と引き換えてもらったりする。テレックスも予約の確認とヴィザの発行に関することで必要らしい。
日本でソ連のヴィザをとるには、ソ連内での旅程をすべて決めて、移動と宿泊の予約を日本の提携旅行代理店とソ連国営旅行社を通じて入れ、料金をすべて払い込むと発行されるバウチャーとテレックスが必要なのだ。
旅行代理店に行き、料金の残額を払って、バウチャーとテレックスを受け取り、再び、ソ連総領事館へ向かった。
「こちら豊中市ソビエト連邦総領事館前派出所」前で再び職務質問を受けた。名前を訊ねられ、「どちらの?」と住所まで訊かれた。その昔はソ連を旅行しただけで共産主義者扱いされたということだが、ぼくの名前と住所はいまでもどこかのブラック(またはレッド)リストに残っているのだろうか。
バウチャーとテレックスとパスポートを渡して、二度目の訪問も終了。
一週間後、三度目の訪問。もちろん三度目の職務質問。
ついにソ連のヴィザを手にした。当時のソ連のヴィザはパスポートに押すタイプではなく、別紙だった。
会社を辞め、ドルのトラヴェラーズ・チェックなどを買い(ちなみに当時の売値は百四十八円)、七月十五日、航空運賃の高くなる夏休みのシーズンが始まる前に日本を発った(これが生まれて初めて乗った飛行機だった)。
つづく
[脚注]
-
一度くらい海外旅行をしておこうと思った
当時はこれで旅の面白さにはまってしまうなど全く予想していなかった。
-
ウラジオストク〜ハバロフスク
たしか当時、外国人はウラジオストクに入れなかったのでハバロフスクから乗っていたように記憶している。
-
ソビエト連邦がまだ存在していた
ソヴィエト社会主義共和国連邦が崩壊したのは一九九一年十二月。
-
香港行きの片道航空券の手配
香港経由で中国に入ることにしたのも、日本で中国のヴィザを取るのが面倒なため。このときは上海行きの船の鑑真号で行くことはあまり考えていなかった。よく憶えていないが、船で取ってもヴィザ代が高いのと、なるべくたくさんの国に行きたいと思っていたためだろう。
-
ソ連総領事館
現在もロシア連邦総領事館と名前を変えて同じ場所にあるようだ。交番は今でもあるのだろうか。レーニンの胸像はどう処分したんだろう。
在日ロシア連邦領事部ホームページ
-
ピンク電話
ひょっとしてピンク電話も説明しないと分からない人がいるだろうか。竹内都子と清水よし子の二人によるお笑いコンビ…ではなく、いやらしい声が聞こえてくる電話…でもない。着信ができるコイン式の小型の公衆電話、であってるかな。
-
SDI
アメリカのレーガン政権が一九八〇年代に始めた、飛来する敵(ソ連)の核ミサイルを迎撃するために計画した戦略防衛構想(Strategic Defense Initiative)、いわゆるスターウォーズ計画のこと。
-
ソ連のヴィザ
日本でヴィサを取らなくても直接近隣国へ行ってシベリア横断列車の切符を買ってしまえば、ホテルの予約などはしなくてもソ連の七日間有効のトランジット・ヴィザ(通過査証)が出るということは、日本で準備しているときには全く知らなかった。これだと滞在期間が短いのでモスクワ以外で列車を降りることはできないが、ほんの数万円しかかからないということだった。
前略、
安宿の部屋のドアに自分の南京錠で二重に鍵をかけると安全性は増すのだろうか?
以下の考察は部屋に鍵がまったくないとか、南京錠だけという安宿は関係がない。また、「ホテルのドアに南京錠でどうやって鍵をかけるの? 鍵はいつもカードだよ。っていうか、南京錠ってなに?」という人も以下の文章は読むだけ無駄だ。
安宿のなかには、ドアにちゃんと鍵は付いているが、ドアの外側に宿泊者が自分の南京錠などで二重に鍵をかけられるように金具がついているところがある。ぼくも気が向いたときはマイ南京錠をとりだして二重に鍵をかけることがある。かけないことも多いのだが、これをすることによって本当に安全性が増すのかということをちょっと考えてみようと思う。
泥棒の気持ちになって考えてみよう。何事も相手の気持ちになって考えるのはよいことである。
あなたは泥棒である。今、ひとけのない安宿の廊下に立っている。まず南京錠の付いていないドアの前に立ってみる。ノックをしてみよう。返事があった場合はすぐに立ち去らなければならない。返事がなければ、ドアを開けてみよう。
ドアに鍵がかかっていた場合、あなたは鍵をやぶらなければならないが、あなたは泥棒だからそれくらいのことはできるだろう。
ドアを開けてみて、考えられる状況は三つ。人がいなくて荷物がある。荷物があるけど人もいる。人も荷物もない。
人がいなくて荷物があるというのが、泥棒であるあなたにとって理想的な状況だ。ただし、ドアに鍵がかかっていなくてこの状況だった場合は人がすぐに戻ってくる可能性が大きいので仕事は素早く行わなければならない。
荷物があるけど、人もいるという場合、中にいる人はノックを無視したか、聞こえなかった(iPodを聴いていた)か、寝ていたかということだろう。相手に気がつかれる前にドアを閉めることができればよいが、そうでなかったときはなにか言い訳を考えなければならない。とりわけかかっていた鍵を無理矢理開けて入った場合は、相手を納得させる理由を考えるのはなかなか難しい。相手が寝ていた場合は仕事にとりかかるかどうかはあなたの神経の太さ次第だ。今回、あなたは泥棒ということなのでそれ以上の凶悪な犯罪に進むことは考えないでおこう。
人も荷物もない場合、あなたは空き部屋に入ったのだ。ルーズや宿なら空き部屋に鍵なんかかけない。鍵をわざわざやぶって空き部屋に入った場合、あなたは意味もなくそこで時間をつぶし、誰かに見つかる危険が増したことを認識しなくてはならない。
今度は南京錠のかかったドアの前に立ってみよう。今度はノックをする必要はない。南京錠で外から鍵をかけてある部屋にノックをして中から返事があった場合、それは誰かが監禁されているということだ。泣き叫ぶ女性や子供の声が聞こえてきた場合、あなたは仕事をするどころではなくなってしまうだろう。
ノックはせずにいきなり仕事にかかればよい。あなたは泥棒だから、二つの鍵くらい開けることはできるはずだ。ドアを開ければ、そこには誰かが監禁されていない限り人はいないし、空き部屋であるはずもない。南京錠をかけて外に出かけた宿泊者の荷物があるはずだ。さあ、仕事にかかろう。
どうだろう。あなたなら南京錠のかかった部屋とかかっていない部屋のどちらに泥棒に入るだろうか。翻って、あなたは安宿の自分の部屋に南京錠で二重に鍵をかけたいと思うだろうか。
草々
追伸、安易な結論に飛びつかれては困るので、別の考え方もあることを付け加えておいたほうがいいだろう。「リアル・ヴァージョン」だ。
あなたは泥棒である。ちまちまくだらない仕事なんてしてられないと思っている。楽して金もうけができればサイコーだ。宿には南京錠で二重に鍵のかかったドアとかかっていないドアがある。あなたはどっちに入る…。
電気のない旅はいい。
電気がなければ、テレビもカラオケもインターネットもなく、しずかなひとときが過ごせる。ミャンマーでは坊さんが、右翼の街頭宣伝車のようにスピーカーで説法を大音量でがんがん流すところがあるが、停電になればこれも止む。
実際には静かに過ごすにはさらにいくつか条件が必要だ。日常的に停電のある場所の宿やレストラン、商店の一部はエンジン式の発電機を置いていて、停電するといっせいにエンジンが動き出して逆にうるさくなる場合がある。ミャンマーなどの車の多い国だとかなり田舎へ逃げる必要がありそうだ。
電気がないのがいいなんていっているのは、一時的に滞在する旅人の勝手な意見だと思う。ラオスのデット島で泊まった宿の二十三歳の娘さんは、その電気もほとんどなく、車も水道もない、テレビもカラオケもインターネットもない(ラジオはあった)、メコン川に浸かって体を洗う島に生まれ育った。雨季にはメコン川の水量が増え日常的に床下浸水状態になり泊まり客も来なくなると話していた。
都会から短期間来た旅人がお気楽に「いいところだ」と繰り返すと、けなされるよりはましでも、複雑な気持ちかもしれない。
一時的にでもそんな旅をしているうちに、ぼくの日本での生活も少しだけ変わってきた。
昔に比べるとぼくの生活はシンプルになった。昔はいろんなものをため込んで持っていたのだが、背中に背負えるものだけで何年も生活できることが分かってからは、なるべく物を持たないようにしようとするようになった。
一番分かりやすい変化は、テレビを見なくなったということだろうか。昔はテレビやビデオが好きで録画した映画やテレビのテープ(ベータ方式!)が山のようにあったのだが、テレビのない生活を始めて十年近くになる。
テレビを見てないとテレビドラマやコマーシャルの話題には入れないし、アイドルやお笑いタレントの顔と名前が一致しなくなるし、年末の「今年の流行語」なんてものも半分以上は初めて聞く言葉だったりする(ギター侍ってなに?)。
でもテレビがなければ、テレビ番組表やビデオ録画などというものにわずらわされず、液晶テレビ、プラズマテレビ、DVD、HDDビデオデッキなどという製品にも無関係でいられる。地上波デジタル放送? どうぞご勝手に、という感じだ。無意味にテレビを見ていた時間が自分の時間として使える。
なかでも最大の利点を教えよう。
NHKの集金人が来た時に、何の後ろ暗いところもなく、絶対の自信を持って、「見てない! 失せろ! おとといきやがれ!」と言えるのだ(集金人はテレビのないことを信用してないようだが…)。
でも、日本で電気のない生活をするのはかなり難しそうだ。
草々
(「野宿野郎」2号より転載)
ラオスやミャンマーでも停電の多い町は多かった。
ラオスでは石油はほとんど産出せず、発電のかなりの部分を水力発電で行っている。ミャンマーは産油国なので火力発電が盛んだが、水力発電にも力を入れており、電力の数割は水力で行っている。
水力発電は雨季のあいだはいい調子なのだが、乾期に入り、川の水量が減りだすと発電量も減るので乾期の終わりになると停電が多くなるらしい。ラオスが水力発電で作った電気を隣国のタイに売っているというのは有名な話だが、自国で余った分を売っているというより売れるものがほかにはあまりないので自国で必要な分も売っているということらしい。
ミャンマーでは、首都のヤンゴンはたまに停電があるくらいだったが、地方に行くと停電が多くなり、週に三、四日だけ電気が来るというところもあった。
ラオスの北部ノンキャウという田舎の村では電気が来るのは日没から三時間ほどだけだった。村の一本だけのメインストリートを電気のなくなったあと歩いていたら道の真ん中で寝ころんでいた犬のしっぽを踏んでしまったほどだ。しかし、日本からきたぼくには全くの暗闇でも地元の人にはそうではないらしい。ある夜、小さな懐中電灯で暗闇をおそるおそる歩いていると、暗闇の中からぼくに話しかけてくる声があった。声のするほうを向いても暗闇しか見えず、しばらく懐中電灯でさがすと知り合いになったラオス人がなにも持たずに真っ暗な中を歩いてくるのが見えた。
ラオスの南部、カンボジアとの国境近くのメコン川の中にシーパンドン(四千の島)と呼ばれる小さな島々がある。関係はないが、ドレッシングの名前で有名なサウザンド・アイランド(千の島)はカナダのセント・ローレンス川の中にある。
そのシーパンドンの中のひとつであるデット島に滞在した時も電気は限られたもので、ぼくの泊まった宿には電気が引かれてなかった。
島のふちは一、二メートルのでこぼこの未舗装の道になっていて、その外側はそのまま数メートルのがけになっていてメコン川に落ちている。街灯などはもちろんなく、小舟で行き来するだけの島なのでトラクターが数台あるだけで車は全くなく、日が落ちるとほぼ真っ暗闇だった。
ただの真っ暗な村なら歩いていても、こけるか、ぶつかるか、犬のしっぽを踏むかぐらいで命にかかわることはないのだが、そこはそうではなかった。明かりを持たずに外に出て、日が暮れてしまうと、足を踏み外して崖下のメコン川に転げ落ちる危険があるのだ(実際に落ちる旅行者もいると聞いた)。
ある日、真っ暗な中を懐中電灯を持ち、またおそるおそる歩いて細い道を宿に帰ろうとしていたら、いきなり目の前で甲高い金属音がして、ぼくは声を上げて驚いてしまった。目の前には笑っている地元の島民が自転車に乗って止まっていた。もちろん自転車にライトなどは付いていない。もうびっくりである。道の一方は崖になってメコン川に落ちているでこぼこのほとんど真っ暗な道で、ぼくなら懐中電灯がなければ四つんばいになって這っていかなければ前に進めないようなところを平気で自転車に乗っているのだから。でも、むこうにしてみればちゃんと見えているから自転車に乗っているわけで、こっちから見えているのだから、向こうもこっちのことも見えて当然だと思っていて、何であの外国人は自転車がきているのによけないんだと不思議に思っているかもしれない。
つづく
中東を廻っていたとき、ヨルダンからシリアに入ってダマスカスの宿でのこと、ぼくの訪れた安宿にはあまり空き部屋が残っておらず、安いが窓がないという部屋に通された。ダマスカスにはそれほど長く泊まる予定でもなかったのでそこに決めて、昼間から電気をつけて荷をほどいて休んでいると、突然停電した。このあたりでは停電は珍しくないし、宿のヒューズがとんでしまうこともある。
話が少し脱線するが、ぼく自身が宿のヒューズをとばしてしまったことも一度や二度ではない。ぼくは旅に必ずコイル・ヒーターなどと呼ばれているコンセントにつなぎ、ヒーター部分をコップの水に突っ込むとお湯が沸かせる器具を持っていく。これがあれば電源と水道さえあればどこでもお湯ができ、コーヒーや紅茶、インスタントラーメンやみそ汁などが飲めるので、ぼくの旅には欠かせない道具になっている。
旅に出た先で買えば値段は安いし、便利この上ないのだが、作りが雑なものが多く、使っているうちにヒーターのコイル内部に水が入り込んで漏電するようになってくるものがある。湯を沸かしているときにコップの取っ手を握ったら電気で手がしびれたこともあった。そして、ある日突然、壊れて湯を沸かせなくなってしまうのだが、この時、電気がショートしてしまって宿のヒューズをとばしてしまうことがしばしばあるのだ。自分の部屋のヒューズをとばすぐらいならたいしたことはないのだが、場合によっては宿中が停電してしまったりすることもあって大変ばつが悪い(でも知らんふりをする)。途上国では日本のようにすぐ元に戻せるブレーカーではなく、文字通りヒューズを使っているので直すのに手間と時間がかかるのだ(もうヒューズなんか知らない人も多いかもしれないので説明すると、ヒューズというのは電気を通す金属で過剰な電流が流れると溶けて電気を遮断する。なので溶けてしまうと新しいものに付け替えなければならない)。
一度など、宿のロビーで湯を沸かしていたらコイルヒーターがものすごい火花をあげて小爆発を起こし宿を停電させてしまったことがあった。
話を戻すと、この時のダマスカスの宿の停電は真っ暗な部屋でしばらく待っていてもなかなか復旧しなかった。宿のオヤジさんに訊ねると、そこでは十四時から十八時まで毎日停電するということだった。
シリアはアラブの国にもかかわらずアラーの贈り物である石油がほとんど産出しないために慢性のエネルギー不足で、水不足の時に断水をするように、一日のうちの一定の時間「断電」をしているのだった。
ダマスカスの後、パルミラへ足を伸ばした。
パルミラは砂漠の中のオアシスにあり、紀元前後にシルクロードの隊商都市として栄えたが、後にローマ帝国に滅ぼされ、ギリシャ・ローマ文化に影響を受けた神殿や劇場などの遺跡が残っている。
この町でもしょっちゅう停電が起こっていたが、定期的なものではなかった。ある日、日の高いうちに始まった停電は日が暮れたあともつづいた。部屋にいてもしょうがないので夕方、寝袋を持って屋上で寝ころんでいた。空が暗くなるにつれ星が瞬きはじめた。この町は砂漠の中のオアシスの町なのでまわりに空気をよどませるものはなにもなく、乾燥しきっているので雲も全くない、都会で星を見えにくくしている要因のひとつである町の明かりも停電のために(全くというわけではないのだが)ない。
空には満天の星が広がっていった。日本の都会で見る何百倍、何千倍の星だろう。天の川がはっきりと帯状に見えた。星くずとはよくいったものだ。星が多すぎて漆黒の空にほこりを散らして汚れているようにも見えた。
つづく
前略、
電気のない旅が楽しくなってきた。
最初に電気のない旅を経験したのはカナダだっただろうか。カナディアン・ロッキーの南の入り口の町のバンフまで来て、その場の思いつきで自転車を買ってロッキー山脈を縦走してみた。山脈を縦走するといってもそこにはちゃんとした舗装道路(ひび割れだらけだけれども)が通っていて、車や観光バスだと半日で通り過ぎてしまうところである。いろいろ調べてみるとロッキーの道路沿いには数十キロごとにユース・ホステルがあるので、自転車さえあればテントや調理道具などの重装備をする必要がなく、バスで半日で観光して通り過ぎてしまうよりじっくり楽しめると思ったのだ。
山に入って最初のうちはユース・ホステルも町と変わらない設備だったのだが、国立公園内に入っていくと開発の制限があるので宿は山小屋風で設備は最低限のものになり、水道も電気も電話もなくなった。
調理はプロパンガス、照明はガスかオイルランプ、暖房はガスや薪、飲料水は近くの小川からポリタンクで汲んできて五分間ほど煮沸消毒する。小川の水はロッキーの雪解け水なので冷たく澄んでいて、一見何の問題もなさそうなのだが、ビーヴァーのおしっこに含まれる成分でかかるというビーヴァー・フィーヴァーという熱病になることがあるらしい。
あるユース・ホステルには冷蔵庫があったので驚いた。電気のない宿にある冷蔵庫なのに開けるとちゃんと冷えていた。よくみるとガス管がつながっていて、ガス冷房という仕組みがあるとはしらなかった当時はふしぎに思ったものだった。
別のユース・ホステルではお客が宿泊料をクレジット・カードで払っていた。電気も水道も電話もなく、トイレも離れの個室で穴の中にするような一泊八ドルほどの宿でも、さすがはクレジット社会の北米なのである。
舗装道路が通ってはいるものの、やはり山の中を自転車で行くのは坂道がかなりきつく、途中の宿では雪に降りこめられてなかなか出発できなかったり、食料が足りなくなって団体客(自転車で旅するツアー客がいた)にめぐんでもらったりして大変だったが、雪山や川、湖、大氷河は美しく、鹿やビッグ・ホーン・シープ、マウンテン・ゴート、黒熊、グリズリー・ベアーなど野生動物も見れて、バスで半日で通り過ぎるよりはよっぽど楽しい経験ができた。
つづく
バルト三国にいったのは一九九三年のことだった。
エストニア、ラトヴィア、リトアニアのバルト三国が独立したのは一九九一年のことでそのときから注目はしていた。旅人は新しく独立した国や個人旅行が許されるようになった国などがあると行ってみたくなるものなのである。しかし当時バルト三国の旅の情報は少なく、英語のガイドブックにようやく少しずつ情報が載りはじめたというところだった。現地の近くまで行って何の情報も入らなければ行くのはあきらめようと思っていたのだが、ポーランドのワルシャワまで行くと少しずつ情報が入り始めた。ユース・ホステルには同じくバルト三国へ入ることを計画している女性がいたし、掲示板にも情報が張り出されていた。そしてそこのユース・ホステルに滞在中にバルトから帰ってきた旅人がきたことによりぼくはバルト三国に行くことを決めた。
リトアニアの首都ビリニュスは一番高い建物が教会の尖塔というような田舎で、ラオスのヴィエンチャンが大都会に見えるほどといえば東南アジアをよく旅する人たちには分かりやすいかもしれない。
ラトヴィアの首都リガはかなりロシアっぽい都市で、この三国ともそうだったが花屋が多かったのが印象に残っている。
エストニアの首都タリンは三国の中では一番進んでいる町だった。フィンランドが海を挟んですぐ向かいでそこのテレビやラジオを常に見て聞いていたというのも関係があるらしい。エストニア語とフィン語は同じ語族に属していて、互いに理解し合えるほど似ているらしい。それらのお手本を長年見ていただけあってか、独立後の彼らは変化も早かったようだ。独自のなかなかかっこいいファスト・フードの店がすでにありパスタやアイスクリームなどを売っていた。
タリンの旧市街はとても美しかった。小さな丘の上に立っている坂の多い旧市街はとても絵になった。もう今はかなり観光地化されてしまったと聞いているが当時はまだそれほどでもなかった。
旧市街を観光中、日本人の若い旅人にあった。彼はフィンランドから船で入ってきたということだったが、彼のこの国の情報源は日本で買った「ソ連」のガイドブック(バルト三国に関するページが数ページ含まれている)だったので安宿の情報などは全くなく、来た時は安宿をかなり探しまわったそうだが、見つからなかったので仕方なく旧ソ連系の国営ホテルだったところに大枚五十ドルも払って泊まっているとのことだった。
彼はその日のうちにフィンランドに帰るということだったので、ぼくが四十クローニ(約三百六十円)の宿に泊まっていることは内緒にしておいた。
ガイドブックのない旅にあこがれる。
たいした計画も立てずにガイドブックも持たずに旅立ち、その日の気分で適当な乗り物に乗り、気に入ったところで降りて、地元の人の話を聞きながらどんなふうに過ごすか決めて…。
でも多分次の旅をするときもいろいろ調べて計画を立ててしまうに違いない。
草々
(「野宿野郎」1号より転載)
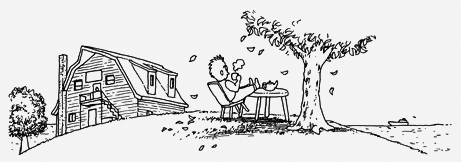
東ヨーロッパにはユース・ホステルは少ないが、全般に物価が安いのでふつうの宿に安く泊まることができる。でも宿の絶対数が少ないところが多く、そういう国ではプライヴェイト・ルームというシステムのあるところが多い。
プライヴェイト・ルームというのは空き部屋のある一般の家庭が旅行者に部屋を貸すシステムで、観光案内所などに登録してあるのを紹介してもらう場合が多 い。イギリスなどのB&B(ベッド・アンド・ブレックファスト)に近いが、東欧の場合は本当に一般家庭の空き部屋に泊まらせてもらう感じに近いので当たり 外れはあると思うが、地元の人のうちににおじゃまできてなかなか楽しい。
ハンガリーのブダペストではプライヴェイト・ルームもかなり商売として成り立つようになっていて客引きまで行っているところが多かった。ぼくの泊まった プライヴェイト・ルームにはこの頃旅の途中の日本人が住み込んでいて、ベッドと食事だけもらって無給で客引きなどの「番頭」業務をしていた。
そこには他にも面白い日本人の旅人がいて、我々から「ホームレス山田」と名付けられたその男はぼくがブタペストの駅に着いた時に、プラットフォームにぽつんと立っているのを見かけていた。しかしその時は声を掛けるわけでもなく通り過ぎた。
そのプライヴェイト・ルームに投宿した後、この宿の番頭さんも客引きの際に彼に駅で会い、彼は我々の宿にやってきた。そして彼は驚異の超異次元体験を我々に聞かせてくれた。
ホームレス山田はその前日にブダペスト東駅に着いた。ブダペストにはプライヴェイト・ルームの数が多いので過当競争になり駅での客引きが当たり前になっ ている。彼はある客引きと交渉して、その人が紹介するプライヴェイト・ルームに泊まることにした。そこで数日分の宿代を払い、彼はさっそく町へ観光に出 た。
夕方、彼はその日の観光を終え自分の宿に帰ることにした。しかし彼はこの時すでに知らぬ間に恐怖の超異次元空間にはまり込んでしまっていたのだった。彼 はいくら歩いても自分の宿に帰りつけなかった。いくらさがしても歩き回っても自分の宿を見つけることはできないのだった。彼のまわりの空間がねじれてし まったのか、知らぬ間にパラレルワールドにワープしてしまったのか、知らぬ間に宇宙人が彼を拉致し記憶を消してしまったのか、あるいは彼の宿は消滅してし まったのだろうか…。
彼は迷子になってしまったのだった。
彼は自分の泊まっているプライヴェイト・ルームの場所が分からなくなってしまったのだ。彼はこの異国の町で迷子になり、完全にパニックにおちいり狂った ように町を歩きまわったが、自分の泊まっている場所、そしてその時にもっていた手荷物以外のすべての荷物が置いてある場所は見つけられなかった。
彼がこの日、自分の宿を見つけることを断念した時には夜もとっぷりと暮れていたため、彼は小さなデイ・パックを持っただけで百ドル以上する高級ホテルに泊まったそうだ。
その次の日、つまりぼくがこの町に着いた日、東駅でぼーっと立っている彼をぼくが見掛け、その後番頭さんが声を掛けた。彼がそこにいたのはそこで待っていたら前日客引きをしていた男がまた客引きにそこへ来て、彼に会えるかもしれないと思ったからだ。
彼はこの日も宿を見つけられずに(百ドルのホテルではなく)我々のプライヴェイト・ルームに泊まり、次の日ついに二日ぶりに自分の宿を発見した。彼が絶対の自信を持ってそこではない、この通りではないと信じて疑わず探していなかった通りに彼の宿はあったということだ。
この話にはまだちょっとしたオチある。
彼は日本で地図を製作している会社に勤めていたのだ。確かに彼は自分の宿のまわりのことだけは詳しく覚えていた。
つづく
このソ連の旅は例外でぼくの旅のスタイルはだいたい安宿に泊まり歩くというもので、宿を予約したという経験もこのときだけだ。
西ヨーロッパや 北米を旅したときに泊まっていたのはほとんどがユース・ホステルだった。これらの地域でユース・ホステルがなければ同じ予算で行けるとこ ろはかなり限られたものになってしまうだろう。だいたいがキッチンの設備があるので自炊できる。西ヨーロッパや北米ではほとんど自炊して食事していたた め、各地の名物料理というのをあまり食べられなかったのは残念といえば残念なのだが、レストランに行っていればすぐに旅費がなくなってしまって行きたいと ころにも行けなくなってしまったはずなのでこれはあきらめるしかない。
ユース・ホステルはだいたい似たようなところが多いのだが、中にはちょっと変わったところがあって、例えばスウェーデンのストックホルムの港には船のユース・ホステルがある。もちろんもう船としては使用していないのだが、中を改造して泊まれるようにしてある。
カナダのニュー・ブランズウィック州、キャンベルトンには灯台のユース・ホステルがある。現役で現在も使用されている灯台と同じ棟にユース・ホステルがあるのだが、現役の灯台ということで中に入ったり、上ったりはできないのであまり意味はないのだが。
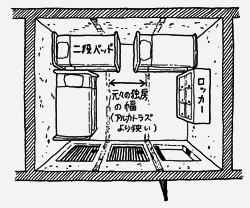 ぼくが今までに泊まったユース・ホステルで一番の変わり種は同じくカナダのオタワのユース・ホステルで、ここは元監獄の宿である。
ぼくが今までに泊まったユース・ホステルで一番の変わり種は同じくカナダのオタワのユース・ホステルで、ここは元監獄の宿である。
中には鉄格子のついた手を広げれば届くほどの幅の狭い独房が並んでいる。その独房を隔てている壁を二つ三つぶち抜いて広げた部屋に二段ベッドが二、三台 入っていて、そこに寝泊まりする。並んだ鉄格子の扉のひとつが開いていてお客はそこから出入りする。鉄製の扉を開け閉めするたびに扉はきしみ音を立てて閉 まりそれが通路に響く。建物の上には昔使っていた公開絞首刑台があり、縄の輪っかも付けてある。
そのユース・ホステルに入所して監房で寝ころん でいるうちに気がついた。ここは独房二つまたは三つ分のスペースに二段ベッドが二つまたは三つ入ってい る。つまり昔は囚人が二、三人しか入っていなかったところに今はその倍の四人から六人を泊めているのだ。我々の扱いは囚人以下なのか! しかもお金まで 払っているのだ。
週に数度、一般の人も参加できる無料の所内観光ツアーが行われる。監房の鉄格子は昔のままで通路から中は丸見えなので一般の観光客がぞろぞろと通路を通って我々収監者を見学していく。
お化けが出るといわれている監房もあって、そこに一晩泊まると次の日はただで泊まれるらしい。お化けの監房はともかく普通の監房でも気持ちが悪いといっ てすぐに出所していく人もいた。鉄格子のきしむ音などはあまり気持ちのいいものではないし、想像力豊かな人は昔同じ場所にいた囚人のことなどを考えてしま うのかもしれない。ぼくは面白くて気に入ったのでオタワではずっと厄介になっていた。
つづく


